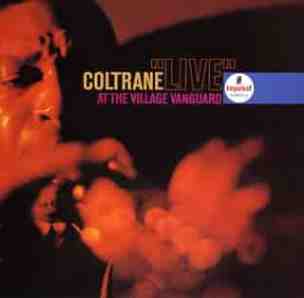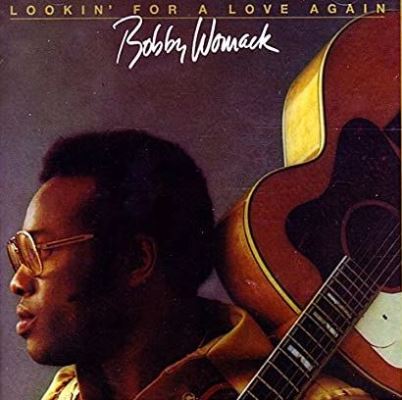ジョン・コルトレーンの
『スピリチュアル』について
▼ ジョン・コルトレーン

「ジャズ」という言葉から、多くの人は何を連想するのだろうか。
この言葉から、即座に「マイルス・デイビス」とか、「ジョン・コルトレーン」などという固有名詞を思い浮かべる人は、それなりに “(オールド)ジャズファン” といってよさそうだ。
でも、私が昔通っていた居酒屋のオバサンは、「プレスリー」も「ビートルズ」もみな「ジャズ」といっていた。
戦後間もない時代、進駐軍といっしょに入ってきたアメリカ音楽をすべて「ジャズ」と呼んでいた時期があったから、高齢シニア世代のなかには、今でも洋楽全般を「ジャズ」と呼ぶ人たちがいるのは確かだ。
ただ、今の若い人たちがイメージする「ジャズ」は、夜景のきれいなバーラウンジなどにかかるBGMというような印象ではなかろうか。
なにしろ、ジャズは音としての抽象度が高いから、特に耳障りの悪いものでないかぎり、店舗のBGMとして流れていても、ほとんどのお客が気楽に聞き流すことができる。
それでいて、この手の音楽は店内を大人っぽい雰囲気に包む。
だから、最近はお洒落な和風割烹やお蕎麦屋さんなんかでも流していることがある。
今では、そういうBGM的な使われ方が多い「ジャズ」ではあるが、かつてはポピュラー音楽のなかで、もっとも先鋭的で、革新的な音楽と目されていた時代があった。
1960年代である。
この時期、ジャズを聴く人間は、前衛的な知的エリートだった。

小説家の中上健次(写真上)が、新宿のジャズ喫茶に入り浸りながら、小説家を目指すための思索を練っていたように、60年代は、ジャズが「文学」や「アート」、「思想」や「哲学」などといちばん強く結びついた時代だった。
▼ 中上健次のジャズエッセイ集。
有名な「破壊せよ、とアイラーは言った」(1979年)も収録されている

村上春樹も、60年代の後半にジャズ喫茶に入り浸った口で、70年代に入ると、自分でジャズ喫茶(「ピーターキャット」)を経営している。
この時代、ストーリー展開にジャズが絡んでくる小説も多かった。
その先駆けとなったのは、石原慎太郎の『ファンキー・ジャンプ』(1959年)だった。
これは、薬物依存症のジャズピアニストを主人公にした小説で、文体そのものがジャズのテンポとリズムを再現するという実験的なものだった。
五木寛之は、ジャズ好きの少年を題材にした『さらばモスクワ愚連隊』(1967年)で小説家デビューを果たし、『青年は荒野をめざす』でもジャズをテーマにした。
▼ 『さらばモスクワ愚連隊』の朗読CD

私が、はじめてジャズ喫茶に足を運び入れたのは、高校生のとき(1967年頃)だった。
学生服を着たまま、吉祥寺本町の「Funky(ファンキー)」に通った。
「Funky」は、今でこそ、「バー&キッチン」を謳うレストランだが、60年代はバリバリの本格的ジャズ喫茶だった。
▼ 当時の「Funky」のマッチ

その頃の店は今の「パルコ」の敷地内にあって、店の前には「スカラ座」という映画館があった。
その辺りはかなり広域にわたって再開発が進んだので、今はもう当時の面影を探すことはできない。
▼ 「Funky」のオリジナルコーヒーカップ。
こういう一本足デザインのカップはほかの店で見ることはなかった

余談だが、この当時の「Funky」は、桐野夏生・作『抱く女』のなかでは「COOL」というジャズ喫茶名で登場。作品のなかで当時の店内の状況がレポートされている。
▼ 桐野夏生 『抱く女』

私が「Funky」に入り浸るようになったのは、高校の先輩たちの影響が強い。
当時私は、新聞部と演劇部に所属していたが、どちらの先輩たちもみなジャズを聴いていた。
ジャズ専門誌である『スイングジャーナル』を小脇に抱えて部室に入ってきた先輩たちが、その雑誌が主宰するディスク大賞で、『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン』が第一回目の金賞を受賞したということを話題にしていたことを記憶している。
▼ オーネット・コールマン 『ゴールデン・サークル』

オーネット・コールマンもスイングジャーナルもよく知らなかったが、そういう知識がないと、新聞部においても演劇部においても、ジャズどころか “音楽” そのものを語れないような風潮があった。
そこで、私は密かにジャズ喫茶に “勉強” に行くことにした。
「Funky」に入り、コーヒーを注文するタイミングで、ウェイターにリクエストを頼み込んだ。
先輩たちが話題にしていたオーネット・コールマンという人の『ゴールデン・サークル』というアルバムを聞いてみようと思ったのだ。
Ornette Coleman Trio at the Golden Circle - Faces and Places
youtu.be
う~ん ……。
しばらく言葉が出なかった。
私の知っていたジャズというのは、たとえばデイブ・ブルーベック・カルテットの『テイクファイブ』であったり、アストラット・ジルベルトの『イパネマの娘』のようなものだったから、こういう人の意表を突くようなメロディを持つ前衛的なものを “心地よい” と思う感覚が育っていなかった。
しかし、『スイングジャーナル』というのは、当時のジャズ批評の最高の権威だった。
“権威” が間違った評価を下すはずはない。
こういう音を美しいと感じるためには、自分の感性を鍛え直さないといけないと思った。
▼ 「スイングジャーナル」

しばらく、一人だけの修業が続いた。
この時期は、ちょうど前衛的なジャズの最盛期だったから、オーネット・コールマンのようなフリージャズ運動の推進者はヒーローだった。
間違っても、アントニオ・カルロス・ジョビンのボサノバや、リー・モーガンの「サイドワインダー」や、キャノンボール・アダレイの「マーシー・マーシー・マーシー」のような軟派系ジャズは、「Funky」ではほとんどかからなかった。
なにしろ、ポール・ニザンの『アデン・アラビア』とか、羽仁五郎の『都市の論理』、吉本隆明の『共同幻想論』などという本を読んでいるお客さんがいたりする店である。
そういう客は、デイブ・ブルーベックの「テイクファイブ」などが流れて出すと、本から顔を上げ、「あ~あん?」と眉をしかめ、「リクエストしたやつは誰だ?」と蛇のように鎌首をもたげて周囲を見回したりする。
だから、うかつなリクエストなど出せないのだ。
硬派の客たちのリクエストで人気が高かったのは、やはりジョン・コルトレーンのアルバムだった。
レーベルでいうとインパルス時代のものが多く、『至上の愛』、『クル・セ・ママ』、『アフリカ』などという作品がよくかかった。
どれも、薄暗い熱帯ジャングルで、ターザンが道に迷っているような音だと思った。
▼ 「アフリカ」

最初は修行のつもりで、目を閉じ、じっと耳を澄ませていたが、やがてこの手の音に、自分の身体が徐々に反応し始めた。
身体の血管が膨張を開始し、大量の血液が体内を駆け回り始めたような感覚といえばいいのだろうか。コルトレーンのサックスには、リスナーの心臓の鼓動を “アンプ” をつないで増殖させるような作用があったのだ。
▼ ジョン・コルトレーン 「スピリチュアル」
John Coltrane - Spiritual - Live At The Village Vanguard
youtu.be
なかでも、1961年に、ニューヨークのヴィレッジ・バンガードで行われたライブを音源とする『Live At The Village Vanguard』は、すごく好きになった。
そのアルバムのなかでも、特に「Spiritual(スピリチュアル)」には魅せられた。
最初、何やらものものしいイントロが流れる。
前衛劇などを上演する芝居小屋で、幕が上がる前のような緊張感がここで生まれる。
そのイントロ部分を1分ぐらいコルトレーンが吹いた後、おもむろにリズム隊が演奏に参加してくる。
この入り方のタイミングが絶妙だ。
流れるリズムの基本は3拍子。いわゆる “ワルツ乗り” だが、複雑なシンコペーションが入ってくるため、得も言われぬ浮遊感が漂ってくる。
そのため、前衛ジャズ的な刺激のなかに、ダルでレイジーなアンニュイが生まれ、それが心地よい催眠効果を誘い出す。
そういう呪術的なリズムの中を、たゆたうように虚空をたなびいていくコルトレーンのサックスは、まさに “神の吐き出した空気” そのもので、「スピリチュアル(心霊的)」というタイトルの意味も十分に伝わってくる。
こういう精神性の強いジャズは、やはり “頭で聞く” 音楽なのだ。
ロックンロールやR&Bのように、“頭が理解する前に腰が揺れる” という音楽ではない。
▼ ヴィレッジ・バンガードのコルトレーン
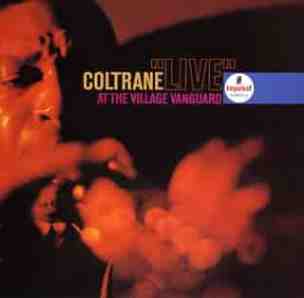
コルトレーンの「Spiritual(スピリチュアル)」のような曲が心地よい、と感じるためには、ある程度知的な訓練を通じて、脳内に受容体を作らねばならない。
ディスコでR&Bを聞けば、自然と足がステップを踏み出すかもしれないが、この時代のジャズを味わうためには、少なくともジャズの基礎知識を記した書籍の1冊ぐらいは読む必要があった。
私は、相倉久人氏の著書『モダン・ジャズ鑑賞』(1963年)を読んで、60年代の広範なジャズシーンの状況を概括することができた。
もちろん、それによって、コルトレーンという音楽家の概要をつかむこともできた。
▼ 相倉久人 『モダン・ジャズ鑑賞』

コルトレーンは人生の後半戦において、西洋音楽の規範から抜け出し、広く、アジア、アフリカ、アラブ、ポリネシアなどのリズムを吸収する形で、人類が積み重ねてきた音楽文化の頂点を極めることに力を注いだ。
そのために、数多くの古典哲学や宗教書にも目を通したと伝えられている。
彼のそのような努力を評価する知的好奇心を持たないと、こういう音楽に体ごと反応することは難しい。
つまりは、リスナーの想像力が試されるのだ。
「脱・アメリカ/脱・文明」を志向して都会の谷間に潜航したコルトレーンの音から、砂漠を吹き抜ける風の気配や、鼻孔を襲うジャングルの木の葉の匂いを想像する。
そうやって、聴覚や視覚、嗅覚まで総動員するような受容体を作り上げないと、コルトレーンの音は身体の中に入ってこない。
▼ ジョン・コルトレーン

彼の「スピリチャル」や、「クル・セ・ママ」、「アフリカ」などを受け入れる受容体ができあがってくるにしたがって、私は小説家の中上健次あたりが追いかけていた “ジャズの精神” がようやく理解できるようになってきた。
つまり、
「こういう音楽こそが、創作活動の刺激になる」
…… そう確信した。
ディスコで聞くR&Bとか、コンサートで聞くフォークソングなどが “消費の音楽” だとしたら、コルトレーンやオーネット・コールマン、アルバート・アイラ―、マイルス・デイビスのジャズは、“生産の音楽” といえる。
そのような音楽を糧として、リスナーが自分自身の創作活動に邁進していくための素材なのだ。
1960年代。
世界の各地で、その国の政権に対する若者の反乱が起こった。
▼ 60年代のフランスの反戦運動

そういう反乱の流れが加速するなかで、規制の秩序を壊すという名目のもとに、新しい芸術運動が生まれ、新しい文化が台頭した。
当然、破壊の後に不毛の荒野が広がったこともあったし、豊饒な土地が現れたこともあった。
前衛ジャズは、まさに、そういう「1960年代」の空気の中から生まれてきたものだし、またそういう時代でなければ、存在できなかった。
▼ 中上健次 著 「破壊せよ、とアイラ―は言った」

オーネット・コールマン
ジョン・コルトレーン
マイルス・デイビス
アルバート・アイラ―
エリック・ドルフィー
ファラオ・サンダース ……
この時代、新しいジャズを創造したミュージシャンたちは、その生み出した作品同様、個人名がさんぜんと輝いている。
ジャズをあまり聞いたことがない人でも、その時代を生きた人ならば、それらの固有名詞をどこかで耳にしたという経験を持っている。
制作者の名がとどろくということは、まさに彼らがアーティスト(芸術家)だったからだ。
「アーチスト」は、庶民が「アート」を求めるような時代でなければ生きられない。
1960年代は、庶民の多くが「アート」を求めた熱い時代だった。
いま、高級バーラウンジや、高級割烹料亭でBGMとして使われている “心地よいジャズ” の制作者を、いったいどれくらいのリスナーが認知できるだろうか。
私は、ジャズメンたちがレジェンドになれた1960年代という時代を、彼らとともに過ごすことができたことを幸せに思っている。