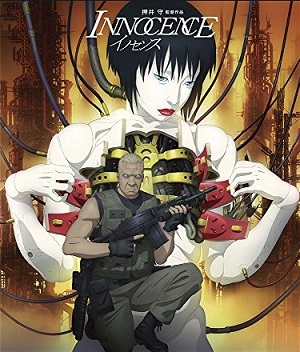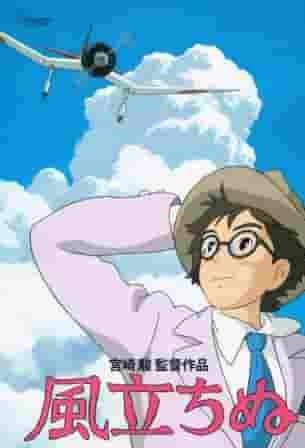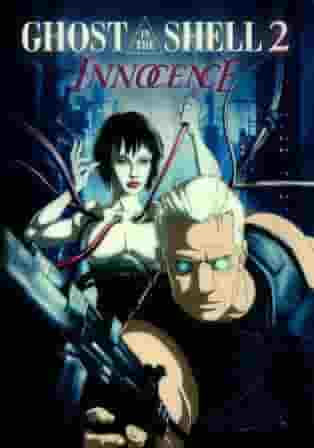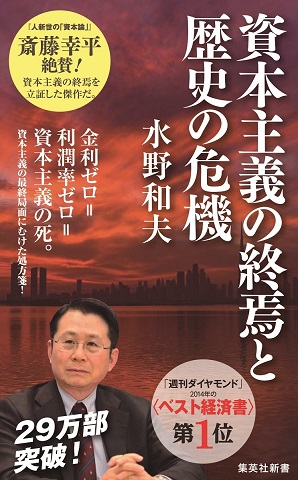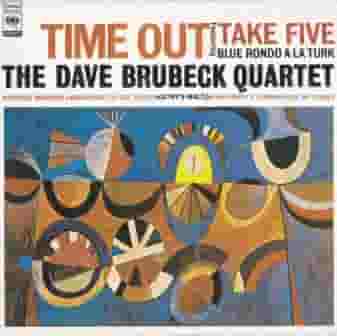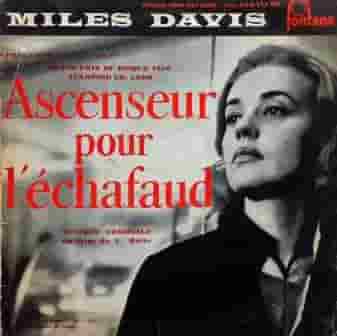去年(2023年)の暮れに近い時期のことである。
2022年に亡くなった映画監督の崔洋一を偲んで放映された『月はどっちに出ている』を、BSシネマで久しぶりに観た。

最初に観たのが1990年代だったから、30年ぶりである。
細部はかなり忘れていたが、それでもやはり、見直して面白い映画だと思った。
在日コリアンのタクシー運転手(岸谷五朗)と、フィリピンパブのホステスであるコニー(ルビー・モレノ)の恋愛を中心に、三流タクシー会社の従業員の間で繰り広げられる「事件ともいえないような “事件”」が淡々と描かれる。
根っこには、在日コリアンが味わってきた「差別への怒り」、「生活苦」、「怨念」、「諦念」 … などといったドロドロしたテーマが横たわっているはずなのだが、映像としては、それがきれいさっぱり濾過(ろか)され、乾いた笑いを湛えた不思議な作品になっている。
特に印象に残るのは、彼らが交わし合う「ドライな人間関係」。
主人公の姜忠男(かん・ただお)は、フィリピン娘のコニーに対してひたすら「愛している」とささやくが、彼の求めるものは往々にしてセックスだけで、そこに「文学」で語られるような “愛” は希薄だ。
一方のコニーは、つきまとう忠男に向かって、
「この腐れチンポ、死んでしまえ!」
「お前のホラ話など聴きとうない!」
と悪態のつきっぱなし。
この “潤いのない” 人間関係こそが、この映画の「乾いた笑い」の正体なのだ。
監督の崔洋一がこの作品をリリースした平成5年は、バブル経済が崩壊し、それまで浮かれていた日本人がみなギスギスした空気に包まれた時代だった。
別の言葉でいえば、「昭和が崩壊」していった時期でもあった。

昭和を支えていた人々の労働環境はどんなものだったのか?
「長期雇用」、「年功序列」といった、サラリーマン生活の安定を保証した企業環境が当たり前に機能していた時代だった。
それが、急激に崩壊していったのが、平成(1989年以降)になってから。
この時期、日本の各企業がグローバルスタンダードとしてのアメリカモデルを導入し、市場そのものが流動的になっていった。
当然のごとく、労働環境も安定感を失い、貧困と経済格差が蔓延していく。
労働者たちの生活スタイルが目まぐるしく変わっていく時代には、人と人の結びつきなど生まれにくい。
温かい人間関係を構築しようにも、昨日までいた同期のサラリーマンが今朝からは左遷されてしまうような職場には、「人の絆」は育たない。
『月はどっちに出ている』という映画は、「昭和」が行き詰まっていく社会風土から生まれた作品といえる。
この映画が誕生した1993年。
実は、「昭和の笑い」を完成させた大ヒット映画シリーズが終焉を迎えようとしていた。
1969年(昭和44年)に第1作が公開され、その後の1995年(平成7年)までに、48作品が供給された『男はつらいよ』である。
ここに登場する渥美清演じる “寅さん” は、『月はどっちに出ている』の姜忠男と正反対をの姿を演じていた。
寅さんは忠男と違って、セックスを目的としていない。
「マドンナ」として登場する女性たちに「恋心」を抱くが、その基本精神は親切心の発揮である。
「相手の身になって生きる」という発想を手放すことのできない寅さんは、相手との間に、自分の欲望を挟み込むことが苦手である。
だから、もじもじしているうちに、いつも寅さんの恋は終わる。
この人情ドラマに、多くの日本人は感情移入した。
寅さんの恋愛は、涙とセットになったものだったからだ。
それに対し、『月はどっちに出ている』の忠男とコニーの恋愛は、どこまでも乾いている。
寅さんとマドンナたちと違い、忠男とコニーには「求める」ものがないのだ。
家庭を求めなければ、「夢」も求めない。
象徴的なことは、どちらも日本人ではないことだ。
在日朝鮮人とフィリピン人。
まさにグローバルスタンダード時代の恋人同士なのだ。
忠男は、「コニーの故郷であるマニラにいって一緒に暮らそう」と言ってはみるが、もとより本気ではなく、当のコニーも忠男の言葉をウソだと知っている。
それでも、2人は、その虚構の「夢」を語り合うことで、かろうじて関係を保っている。
そういう空虚な生活感覚は、忠男が働くタクシー会社の社員たちにも共通している。
彼らはいつも殺風景な会社に寄り集まり、仕事に出かけるとき以外は、ときにケンカし、ヤクザをからない、チンチロリン(サイコロ賭博)で遊び、所在なさそうに虚空を眺めて煙草をふかす。
私にとって、こういう人間関係は、ある意味、新鮮だった。
この映画を通じて、平成という時代を生きた人々の心象風景を学んだような気もした。
【予告編】
最後の展開が秀逸。
いったんは別れたコニーを連れ戻すため、忠男は彼女が住んでいる長野のフィリピンパブに押し掛け、自分のタクシーに乗せて東京に連れ戻す。
「どちらまで?」
人気のない長野のフィリピンバーの前にクルマを止めた忠男は、助手席に乗り込んできたコニーに尋ねる。
「フィリピンのマニラまで」
そう答えるコニーは、もちろんそれを期待しているわけではない。
ただ、そのやりとりに、自分と忠男の空虚な関係をまぎらわす魔法の呪文を手探りしているだけなのだ。
【エンドタイトル】
二人を乗せたクルマが、殺風景な街を滑り出し、歌がかぶさる。
憂歌団の歌う『Woo Child』。
それがエンドタイトルになるのだが、わずか3分ほどの歌にもかかわらず、そこからまったく別の物語が立ち上がってくる。
それは、忠男とコニーの意識の底に埋もれている「根無し草」の慟哭であり、さらにいえば、それは『男はつらいよ』の寅さんが、後ろを向いて流すときの涙のしずくでもある。
こんな歌詞だ。
♪ 風が吹く夜は
いつも眼を覚ます
まるでお前が
窓をたたくようで
耳を澄ませば
声が聞こえる
道に迷って
俺を呼んでるようで
Woo Child 泣かないで Woo Child きっといつか
Woo Child 逢えるから Woo Child 風の中で
これは「鎮魂歌」だ。
昭和の高度成長期に乗り遅れ、貧困と格差社会を味わった人たちに向けた鎮魂歌であり、バブル崩壊後にバタバタと自滅していた人々に向けた鎮魂歌でもある。
そして、個人的な想い出になるが、これは私の親父(おやじ)に対する鎮魂歌ともいえる。
実は、『月はどっちに出ている』という映画は、親父が入院していた病院の部屋で観たものなのだ。
深夜。
午前2時頃だったか。
それまで親父の面倒をみていたくれた介護士の女性が、ちょっとだけ仮眠をとったとき、代わりに親父の世話をすることになった私は、イヤホンを通して、この映画のエンドタイトルに接した。
私は、親父の命がもう長くないことを知っていた。
だから、『Woo Child』の歌詞に登場する “お前” とは、まさに私にとっての親父そのものだった。
(痰を掻きだすために)喉に穴を開けた親父は、もう言葉をしゃべれない。
ただ、吐息だけを苦しそうに繰り返す。
そのかすれた息の合間に、憂歌団の歌が流れる。
♪ 耳を澄ませば
声が聞こえる
道に迷って
俺を呼んでるようで
歌に耳を澄ませながら、私は親父の “声” を聞いていた。