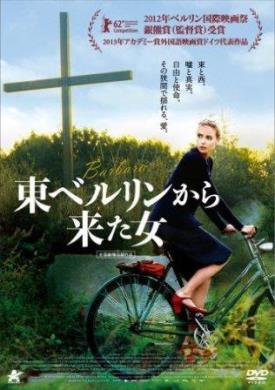「N国党」(NHKから国民を守る党)という政治団体がマスコミの注目を集めている。
2019年の参議院選挙において、代表の立花孝志氏が全国比例区で当選し、生まれてまだ2週間も経たない党だ。
しかし、この立花氏のメディアでの露出度は高い。
彼の登場を批判する人もいれば、評価する人もいる。
私は、この党と立花という代表者に “うさん臭さ” しか感じない。
特に、立花氏が、テレビカメラの前で右手を振りかざし、
「NHKをぶっ壊すぞぉ !」
と雄たけびを上げる顔を見ていると、自分がバカにされたような嫌なものを感じる。
この人の
「NHKをぶっ壊す」
という主張は、真面目なのか。
それとも、冗談なのか。
そこのところが、どうもよく分からない。
「ぶっ壊す!」
と叫ぶとき、立花氏の右腕は思いっきり虚空に突き出される。
しかし、力強く振り上げた拳(こぶし)は、次の瞬間、力なく胸の前にたぐり寄せられる。

そのとき、彼の眼は笑っている。
批判者に対してあらかじめ、
「冗談ですよ」
と言い訳しているような眼なのだ。
その目の中には、ずるさと、したたかさが同居している。
うさん臭さは、すべてそこからかもし出されている。
彼はいったい何をしたいのだろう。
マスコミの情報を拾ってみると、彼の「NHKをぶっ壊す」という主張の中身は、「NHKのスクランブル化を実現する」ということらしい。
すなわち、
「NHKの放送を見たい人だけが受信料を払い、NHKを見たくない人は受信料を払う必要はない」
というシステムを実現したいようだ。
つまり、「NHKから国民を守る」という主張の中身は、「受信料を払いたくない人を守る」ということらしい。
バカな主張である。
私はNHKという放送局が存在することによって、今の日本のテレビ番組が、かろうじて品位と知性を保っていると信じている。
NHKの番組というと、朝ドラと大河ドラマしか思い浮かべない人が多いかもしれないが、BSやEテレも含んだNHKの番組は、知性と教養の宝庫だ。
アフリカの大地に生息する動物たちのドキュメント。
宇宙開発の現在。
歴史上の事件や人物たちの再評価や深堀り。
そして資本主義社会の現在の流れ。
AI テクノロジーの最先端の解説。
そういうものに興味や関心を持っている人からすると、NHKの受信料などほんとうに安いものだ。
番組がいちばん盛り上がったところに挿入されるエゲツナイCMなどから解放される爽快感も捨てがたい。
民放では、CMのスポンサーの意向を外すような企画が組めない。
何事も視聴率優先の企画になるため、国民の多くが煙たがるような社会問題も政治問題も、歴史や文芸においても取り上げられることがない。
NHKは、受信料を徴収しているから、そういう良心的な番組を企画するコストが確保できるのだ。
しかし、NHKに対するこのような評価は、立花氏から言わせると、
「NHKに洗脳されている」
ということになるだろう。
その前に、ひとつ覚えておいていいことがある。
「(誰かに)洗脳されている」
という言辞は、往々にして、それを口にする人間が他者を洗脳するときに使う常套句なのだ。
確かに、NHKという放送局には、いろいろな不祥事もあったし、放送内容が現政権与党寄りだという批判も尽きない。
しかし、私はそういう批判を口にする人間は、より大きなものを見逃していると思う。
NHKの番組に興味のない人でも、なんかの拍子にNHKを見てしまうことはあるだろう。
そして、「けっこう役に立つ番組だったなぁ」とか、「意外と面白かった」と思ったことはあるだろう。
そういう機会を持つことが、実は人間の幅を広げるのだ。
たとえば、欲しい本があったとする。
一番効率がいいのはアマゾンで買うことだ。
しかし、本屋に足を運べば、欲しい本の隣に、興味を引きそうな別の本があることを発見したりする。
そっちの本の方が、実は自分が求めていた本よりもさらに面白いということだってありうる。
NHKというのも、実はそういう要素を持った放送局である。
派手さはなくても、どこかに知性と教養を漂わすような番組が多い。
チャンネルを何気なくNHKに合わせると、「おぉ勉強になるなぁ!」と感心するものがけっこうある。
そういう放送局を “ぶっ壊そう!” と主張することは、国民から知性と教養をはぎ取ろうとする行為以外の何ものでもない。
こういう人に率いられた党が、今回の参院選で98万票を獲得した。
立花氏に好意的な感情を寄せる人は、
「(彼は)既成政党が打ち出せなかった “分かりやすさ” と “面白さ” を選挙戦で発揮した」
と評価する。
私から言われせれば、日本に “バカ” が98万人いたということにすぎない。
そもそも「分かりやすい政治」なんて意味がない。
政治というのは、分かりにくくていいのだ。
分かりにくいものを、自分の頭を使って理解しようとするところに、人間の知性が宿るのだ。
それがその人間のリテラシーとなるのだ。
今回の参議院選挙では、この「N国党」と「れいわ新選組」という新しい党派が躍進したことを受けて、立憲民主党や国民民主党、そして共産党までが「自分たちの主張は分かりにくかった」と反省しているという。
だから、野党はダメなのだ。
繰り返す。
“分かりやすい政治” なんて意味がない。
“分かりやすい政治” というのは、有権者の「知性」ではなく、「感情」に訴える政治のことで、人々に興奮と熱狂を与えることを主目的にしている。
このような政治を「ポピュリズム」という。
ポピュリズムが人々に与える快感とは何か?
既成のルールを壊すことの快感である。
彼らは、
「人間というのは規制のルールを破ることに快感を感じる動物である」
ということをよく知っているのだ。
N国党の主張の根幹にあるものもそれだ。
現在、NHKが国民から受信料を徴収することは憲法で認められており、それを払わないと、“法律違反” になる。
しかし、立花氏はいう。
「法律のなかには、国民が守らなくてもいい法律というものがたくさんあるんですよ。
たとえば、自転車で歩道を走ること。
あれなんか、法律違反ですよ。
だけど守らなくても誰も罰せられない。
つまり、日本の法律には守る必要のない法律がたくさんあるんです。
NHKに受信料を払うという決まりもその一つです」
あまりにも自信たっぷりにいうから、開いた口がふさがらない。

ネット情報によると、N国党の立花氏は、NHKのスクランブル放送を実現するために、安倍政権にすり寄って、それをバーターに「憲法改正派」に与してもいいと安倍首相に持ち掛けるつもりだとか。
なりふりかまわずである。
スクランブル放送の実現が、なぜ憲法問題と結びつくのか。
論理の整合性がまったく取れていない。
立花氏の政治信条というものがますます分からなくなる。