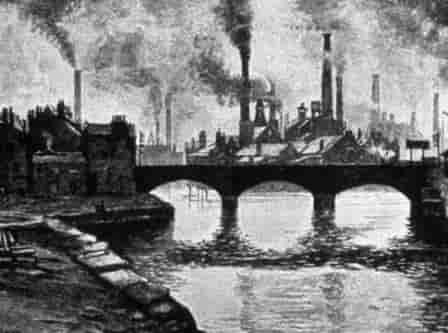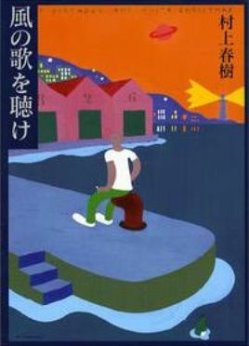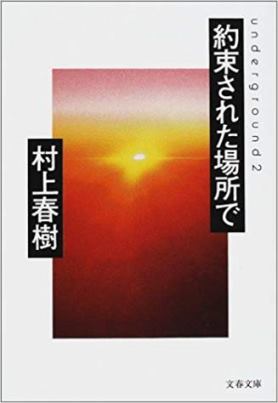現在、日本のマスコミをにぎわせているニュースのひとつに、元・日産自動車CEOカルロス・ゴーン氏の国外逃亡がある。
逃亡先はレバノン。
ゴーン氏の祖父や父の故郷であり、かつ現在の(2人目の)夫人であるキャロル・ナハス女史の出身地でもある。

密出国であるから、日本はレバノン政府にゴーン氏の身柄の引き渡し請求をしたいところだが、レバノン政府は、「ゴーン氏の入国は合法であった」と強く主張し、日本の請求に応える気配はない。
同政府が、ゴーン氏の引き渡しに応じないのは、ゴーン氏が所持している財産の規模がすごいからだという。
ある調査によると、彼が日産のCEOを務めていた時代の年収は19億円。
それが途切れた後でも、残った個人総資産の総額は2,300億円とか。
なんと、これはレバノン政府が所持している資産の3倍ぐらいに相当し、ゴーン氏は、その財産を使ってレバノン経済を全面的にサポートすると約束。すでにレバノンへの大々的な投資を始めているとも。
これでは、レバノン政府もゴーン氏を手放すわけにはいかなくなる。
東京地検は、保釈中にゴーン氏が密出国したため、保釈金の15億円をそのまま没収したというが、2,300億円も持っていれば、15億円程度はレストランのボーイに手渡すチップの感覚であろう。
しかし、上には上がいる。
世界のお金持ちの資産を見ると、「億」の単位を超えて「兆」に至っている。
ちなみに、現在の “億万長者番付” の1位に輝く「アマゾン」のジェフ・ベソス氏の推定資産は17兆円。
2位の「マイクロソフト」のビル・ゲイツ氏の推定資産は14兆円。
以下、2019年の “お金持ちトップテン” は下記の通り。
➀ ジェフ・ベソス(アマゾン) アメリカ
② ビル・ゲイツ(マイクロソフト) アメリカ
③ ウォーレン・バフェット(投資家) アメリカ
④ ベルナール・アルノー(クリスチャン・ディオール、ルイ・ヴィトン)フランス
⑤ カルロス・スリム・ヘル(通信事業) メキシコ
⑥ アマンシオ・オルテガ(ザラ) スペイン
⑦ ラリー・エリソン(ソフトウェア事業部) アメリカ
⑧ マーク・ザッカーバーグ(フェイスブック) アメリカ
⑨ マイケル・ブルームバーグ(ブルームバーグ) アメリカ
⑩ ラリー・ペイジ(グーグル) アメリカ
以下、参考。
㉑ ジャック・マー (アリババ) 中国
……
㊶ 柳井正 (ユニクロ) 日本
……
㊸ 孫正義 (ソフトバンク) 日本
※ 1月1日放映 TBS「サンデーモーニング」より
上位に名を連ねている人たちを見ると、やはりIT 系が多い。
昔は、「石油王」といわれたロックフェラー氏(1839~1937年 推定資産35兆円)、「鉄鋼王」といわれたカーネギー氏(1835~1919年 推定資産32兆円)、「自動車王」のヘンリー・フォード氏(1863~1947年 推定資産20兆円)というようなエネルギー産業や製造業の人たちが上位を占めていたが、ずいぶん様変わりしたものだ。
20世紀から21世紀に向かうときの産業構造の変化が、ここから読み採れる。
現在の “億万長者” たちの資産総額は、合わせるといったいどのくらいになるのだろうか?
あるデータによると、世界のお金持ち上位26人の資産総額は、合計150兆円。
これは下位の38億人の全資産に相当するという。
すなわち、パーセントでいえば1%の富裕層が、世界の99%の貧困層の上に君臨しているという計算になる。
要は、「格差社会」が地球規模で広がっているということなのだ。
どうして、こういう世の中になったのか?
経済学者の水野和夫氏(下の写真右)によると、そもそも資本主義社会がこの世に出現した1870年以来、その恩恵にあずかって「豊かな暮らし」を享受できた人の比率は、地球の全人口のうちの15%程度に過ぎなかったという。
(水野和夫&萱野稔人 著 『超マクロ展望 世界経済の真実』)

氏によると、資本主義の130年の歴史の中で、欧米などの先進国15%の人々だけが、残りの85%の人が住む地域の資源を安く購入し、自国の産業を興隆させ、その利益を享受できた。
このように、そもそも資本主義というのは最初から「お金持ち」と「ビンボー人」という経済格差を前提とした経済システムだったのだ。
ところが、第二次世界大戦後、経済的に大発展を遂げたアメリカを中心に、“膨大な中間層” が世界的に生まれることになった。
この中間層の増大が、あたかも地球全体に繁栄が訪れた(かのように見える)一時代を築いた。
しかし、戦後、アメリカのライバルとしてソ連が力を増し、イデオロギーや軍事力においてアメリカと覇を競うようになってきた。
こうして冷戦時代が訪れたわけだが、1989年、ベルリンの壁が崩壊したことを機に、ソ連が解体され、社会主義陣営と資本主義陣営の競争においては、資本主義陣営が最終的勝利を勝ち取った(と思われた)。
勝者となったアメリカは、その同盟国と一緒に “我が世の春” を謳歌したが、一方では、アメリカの仲間であったはずの日本とドイツの産業が急成長し、経済的にアメリカを脅かすようになっていた。
追い詰められたアメリカは、経済的優位を維持するために、新しい経済戦略を打ち出さざるを得なくなった。
それが、製造部門からの金融部門へ軸足を移す「金融資本主義」だった。
この金融資本主義を根幹に据えた経済・政治システムを「新自由主義」という。
その理論的支柱となったのは、ミルトン・フリードマン(1912年~2006年)だったが、彼の唱えた経済政策を採り入れ、アメリカのプレゼンス(存在感)を再び世界に見せつけたのは、1981年に大統領に就任したロナルド・レーガン(写真下)だった。

同じころ、イギリスではマーガレット・サッチャー政権が誕生し、アメリカと同じように新自由主義的な経済政策で、イギリスの国力を復活させた。
これを機に、「新自由主義」が世界のトレンドとなり、世界各国で、金融や貿易の自由化、規制緩和、企業の雇用調整(リストラ)、国営企業の民営化などが進められた。
そして、これらの制度改革をうまく利用した人々から、これまでになかったような富裕層が生まれ、中間層や貧困層との格差が広がるようになった。
なんていうことはない。
世界は、資本主義の誕生した時代に戻り、その恩恵を受ける少数のお金持ちと、大多数の貧困層とがはっきりと分かれることになったわけだ。
富裕層と貧困層の比率は、昔は15%と85%であったが、今は1%のお金持ちと、99%のビンボー人という比率に変わってきている。
トランプ大統領の躍進、そしてイギリスのEU離脱という現象は、こういう背景から生まれてきたものだといえる。
でも、今はもう眠くなったので、それ以上を述べない。
皆様お休みなさい。