毎年この季節になると、村上春樹がノーベル文学賞を取るかどうかという話題がメディアに採り上げられるが、今年もそれは叶わなかった。

毎度のことなので、“ハルキスト” と呼ばれるファン層の落胆ぶりもそれほど話題にならなかった。
たぶん多くの日本人は分かってしまったのだ。
村上春樹にノーベル文学賞が与えられることは、もうほとんど絶望的な状況になってしまったことを。
いうまでもなく、ノーベル文学賞というのは、その年に世界でもっとも話題性のある文学者に与えられるものである。
“話題性” のなかには、テーマの鋭さ、表現の斬新さ、スケール感の大きさ、哲学性、そしてグローバルな説得力など、すべてが含まれる。
要は、世界中の読書家が、「そうだよね、当然だよね」という納得感のいく作品群を用意した作家に与えられるものである。
今の村上春樹に、それがあるか?
私はデビュー作の頃から村上春樹の大ファンで、『風の歌を聴け』、『1973年のピンボール』などといった初期作品から『羊をめぐる冒険』、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』、『中国行のスロウ・ボート』(短編集)あたりまでは熱中して読み込んだ。
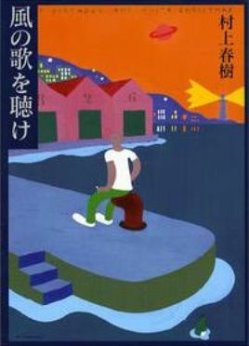
特に、登場人物として「鼠(ねずみ)」が出てくる作品が好きで、主人公の “僕” より、“鼠” のファンであったといっていい。
なんとなく、「つまらないなぁ … 」と感じたのは『ノルウェーの森』からで、以降『国境の南、太陽の西』、『スプートニクの恋人』、『アフターダーク』、『約束された場所で』、『東京奇譚集』、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』などを散発的によみあさったが、初期作品集を超えて感動できるようなものがなかった。
よくいわれる言説に、彼が初期の作品において意識していたことは「デタッチメント」(世界に対する無関心)の感覚であり、その後は徐々に「コミットメント」(世界に対する積極的な関与)をテーマに据えていったというものがある。
その境目がどこにあるのか諸説があるが、多くの読者や評論家は、『ノルウェーの森』あたりからそういう変化が見えてきたという。
もしそれが当たっているのなら、私は、村上春樹の「コミットメント」を志向する作品につまらなさを感じるタイプの人間らしい。
彼の「コミットメント」に対する意欲を端的に訴える2作品として、『アンダーグラウンド』、『約束された場所で』の2作がある。
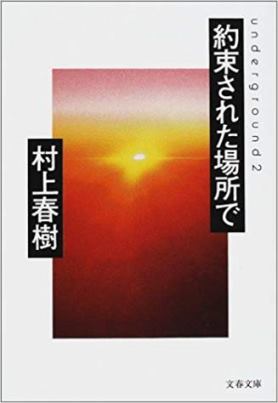
ともに、オウム真理教の犯罪をテーマにしたもので、1作目はオウムの起こした地下鉄サリン事件の被害者に行ったインタビュー集。
そして、2作目はそのオウム真理教信者へのインタビュー集である。
2冊を読んだ感想。
「浅い」
「物足りない」
その二つだった。
オウム真理教の起こした一連の犯罪事件には、とてつもなく広がる “闇” を感じさせた。
頭脳明晰で、学歴優秀な若者たちが、なぜあの無教養なエゴイストである麻原彰晃にマインドコントロールされ、罪の意識もないままに多くの殺人事件を犯してしまったのか。
その謎を解き明かした言説というものは、既存のメディアや評論家から語られることはなかった。
もちろん、型通りの心理学や精神分析学的な解明は横行した。
しかし、あの犯罪には、そのようなありきたりの解釈を跳ねのけるような不気味な強靭さが備わっていた。
そこに “世界的な” 知名度を誇る文学者の村上春樹が切り込もうとしたわけだから、期待しない方が無理だった。
だが、結果的にいうと、あの事件の本質は、村上春樹の真摯さや真面目さをはるかに通り越すところに隠されていて、読み終えた後、「村上春樹をもってしても歯がたたなかった」という失望感があった。
同時に、「村上春樹の限界」を感じた。
そういう私は、いったい何と比較したのか。
一つは、吉本隆明の『共同幻想論』である。
あれは、思想書の体裁をとったエンターティメントだと思うし、作品の質もそれほど高くない。

しかし、「人間というものは何に支配されるのか?」というテーマを追求する激しさにおいて、あの当時の吉本の情熱にはいまだに圧倒される。
もうひとつは、柄谷行人の『意味という病』である。
こちらはシェークスピアの「マクベス」をテーマに据えた文学論であるが、著者自身が後書きで触れているように、連合赤軍のあさま山荘事件を読み解くというモチーフを秘めた作品である。

あさま山荘事件というのは、連合赤軍という左翼過激派が警察と銃撃戦を展開し、逮捕された後、むごたらしい集団リンチ殺人が明るみになったという事件である。
柄谷は、そのことをシェークスピア悲劇になぞらえて思想化した。
書かれたことは、
「マクベスは魔女の予言に接して、何にとらわれるようになったのか」
であった。
つまり、人間を襲う “観念の狂気” がテーマになっていた。
これらのような鬼気迫る評論を経験してしまうと、村上春樹のレポートは軽すぎる。
彼は、絶妙な語彙を操る一流の小説家ではあったが、思想家・評論家としては二流であったといわざるを得ない。
しかし、「デタッチメント」の雰囲気にあふれた初期作品においては、村上春樹の思想家としての限界性は現れなかった。
ところが、「コミットメント」を意識する作品を志向するようになれば、思想性の浅さは致命的になる。
ノーベル文学賞の対象から外れてしまったのは、たぶん世界中の選考員からそこのところを見抜かれたからだろう。
私は、それはしょうがないことだと思っている。
別にノーベル文学賞が取れなかったからといって、彼の小説家としての価値が下がるわけではない。
私は、これからも相変わらず彼の初期作品を愛していくだろうし、場合によっては、温かい目でその感想文を書くだろう。
ところで、日本にはもうノーベル文学賞が取れるような作家が誕生していないのか?
私はそうは思わない。
ノーベル文学賞の選考基準で、「グローバルな視野」というものが重要であるならば、現在のところ、それをもっとも明瞭な形で作品化しているのは、塩野七生氏である。

イタリア・ルネッサンス史、ローマ史、そのほか十字軍、アレクサンダー伝記、地中海海賊の栄枯盛衰記。
彼女の描く歴史物語は、「過去の記録」ではなく、まぎれもなく現在の政治・経済・宗教・哲学の流れまでカバーしている。
“日本人の小説家” として、こういう知の巨人がいるというのに、ノーベル文学賞の選考委員たちはいったいなにを見ているのだろう。