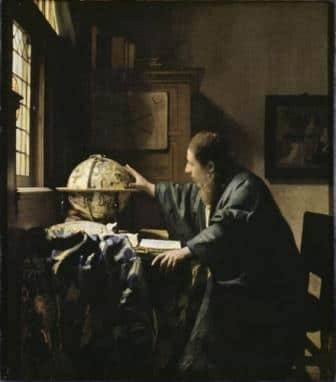習近平主席の訪日の意味
この春、訪日が予定されている中国の習近平(シー・チンピン)国家主席を “国賓扱い” にするかどうかで、いま政権与党内でも議論が起こっている。
「国賓」ともなれば、天皇が主催する国家行事となり、いわばわが国がもろ手を挙げて、現在の中国政府の政治姿勢をすべて承認するということになる。
その中国は、日本に対しては、相変わらず尖閣諸島への領海侵犯を繰り返すのみならず、理由も明らかにせず日本人を拘束し、香港の民主化デモには強硬路線を貫き、台湾の総選挙にも圧力をかけている。
さらに、新疆ウィグル自治区に住むテュルク系住民を強制収容所に送り込み、人権を無視した監視行動を押し進めている。
他国に対する露骨な領土侵害や政治介入。
自国内の異民族に対しては、人権を無視した管理強化。
中国の政治・外交方針は、習近平政権になってから露骨に強圧的な姿勢を強めている。

もちろん、それに対する西側諸国の警戒感も強まってきたが、今の中国はそれを気にする態度も見せず、ひたすら膨張政策をはっきりと打ち出すようになってきた。
「習近平氏の国賓待遇はいかがなものか?」という議論が日本で沸き起こってきたのは、国際社会の世論に反する中国の強硬路線に “免罪符を与える” ことになりかねないのでは? という懸念から生じたものである。
カネにあかして弱小国を味方にする
実際、いまの習近平路線は、「なりふり構わず」という態度を露骨に見せるようになってきた。
この18日に、ミャンマーを訪問した習近平主席は、アウン・サン・スーチー女史と会談。
ミャンマーのイスラム系少数民族のロヒンギャ弾圧を容認したスーチー女史の方針を支持する姿勢を示し、ミャンマーのインフラ整備や通商協定を全面的に支援すると述べたという。
「カネにあかして、弱小国を味方に引き入れる」
これが今の中国の外交方針であり、その矛先は、南太平洋の島々に点在する小国家や経済力に乏しいアフリカの小国家に伸びている。
中国からインフラ整備などで多額の融資を受けても、弱小国にはその返済がかなわない。
そのときは、中国系企業がそこに入り込み、経済を支配し、政治的には親中国系政権を打ち立てる。
習近平主席は、21世紀も後半になれば、アメリカに代わって「中華帝国」が地球の覇者となると間違いなく信じているはずだ。

習近平主席に “焦り” はないのか?
ただ、習政権にまったく焦りがないか? というと、そうともいえない。
中国の総人口は、ついに14億を超えたが、長年にわたる「一人っ子政策」のために人口増加率は鈍化。
今後は、日本以上の少子高齢化社会を迎えるかもしれないと言われている。
そうならない前に、「世界の中華帝国」を樹立するための盤石の布石を敷いておきたい。
最近の露骨な対外姿勢を見ていると、習主席のそういう焦りも見えてくる。
吹けば飛ぶような「自由」と「民主主義」
もし、習近平路線が、東アジア諸国に強大な圧力をかけ始めてきたとき、日本はどうなるのか?
当然、日本も “東風(とんぷう)” に巻き込まれることになるだろう。
その結果、何が待ち受けているのか?
それは、日本人がこれまで信じてきた欧米的価値観を見直さなければならなくなるときが来るということなのだ。
すなわち、「自由」、「民主主義」、「人権」などといった20世紀的価値観が通用しなくなる時代を覚悟しなければならなくなる。
われわれ日本人は、戦後70年、経済的にも、安全保障上においても、アメリカの傘に守られて、ぬくぬくと過ごすことができた。
だから、「自由」、「民主主義」、「人権」などといった欧米的な価値観がフェイドアウトしていくような社会が来ることを想像できなくなっていた。
しかし、すでにアメリカのトランプ大統領は、かつての歴代のアメリカ大統領ほどには、それらの価値に重きを置いていない。
上記の三つの価値観が国民的に共有されるためには、その国を構成する膨大な中間層が必要となるが、アメリカにおいてもヨーロッパにおいても、そういう中間層の没落が顕著になり、富裕層と貧困層の格差が広がり始めている。
そうなると、「自由」、「民主主義」、「人権」などという思想は次第に効力を失っていく。
もちろん日本も、徐々にその気配を見せ始めている。

どこの国も民主主義にかかる
コストを支払えなくなってきた
中国の習近平政権が力を得てきたのは、世界のそういう事情と呼応している。
政治・宗教問題の新しい思想家として脚光を浴びてきた佐藤優氏(写真下)は、習近平政権の台頭をこう分析する。

「習近平やプーチンなどの独裁的な権力者が増えてきたのは、彼らの権力欲だけでは説明できない。
それは国際情勢がきわめて流動的になり、その変化の激しさに、これまでの政治手法が通用しなくなってきたことを物語っている。
すなわち、“民主主義的な手続きによる時間のコスト” に政治が耐えられなくなってきたということなのだ」
この説明をそのまま日本に当てはめると、「桜の会」に象徴されるような名簿・資金の流れを隠蔽しようとする現在の安倍政権のやり方にも、民主主義的な時間コストを省こうとする強引さが感じられるということになる。
中国的な独裁政治を支えるテクノロジー
世界の指導者が独裁的な傾向を強めるようになったのは、何もいま始まったことではない。
第二次世界大戦を引き起こしたヒットラーもムッソリーニも、典型的な独裁者だった。
しかし、あの時代の独裁者たちと、いまの習近平主席では、決定的に違うことがある。
習近平主席は、ヒットラーもムッソリーニも持ち得なかった画期的な民衆支配のテクノロジーを手に入れている。
それがAI を駆使した情報統制システムである。
たとえば「ウィーチャット」などのメッセージアプリをベースにした中国式の「信用スコア」システムがそれにあたる。
現在中国では、この「ウィーチャット」のほかに、アリババグループが展開する「信用スコア」サービスが普及していて、合わせて5億を超えるユーザーに浸透しているという。
これらのサービスは、政府主導で進められており、そこに登録した個人ユーザーのデータは中国政府の監視下に移行されるようになっている。
それが分かっていても、多くのユーザーはもうこれを手放せなくなっている。
なぜなら、たとえば「ウィーチャット」のような「信用スコア」を利用していると、通信機能のほか、QR・バーコード決済サービスを受けられたり、数々のクレジットカードが利用できたり、他のユーザーへの送金などをアプリ経由で可能になるといった途方もない便利さを享受できるからだ。
神戸大学の梶谷懐教授は、このことを次のようにいう。
「中国では、快適な生活を享受するために、政府や大企業に個人情報を提供することを当たり前のように考える市民が増えている。
つまり、中国では、人々の功利主義的な欲求に支えられた “幸福な監視国家” が誕生しつつある」
(朝日新聞 2020 1月16日)
このような社会を支えるものが、AI の進化である。
AI は、人間の顔認証や音声データの管理などを得意とするが、個人の学歴、資産状況、趣味なども簡単にデータ化してしまう。
そのため、中国の若者たちは、婚活も、恋人探しも、「信用スコア」のAI がリサーチした個人データを頼るようになってきたという。
ジョージ・オーウェルの『1984年』の世界が来る
こういう社会の行き先には、何が待っているか?
普通の人間には耐えられないような “過酷な競争社会” がやってくる。
そう答えるのは、経済学者の岩井克人氏(写真下)だ。

「現在、人間の評価は、まだ完全に数値化されていない。人の優しさや上品さというのは、まだ数値に還元されないものとされている。
しかし、そういうものまでが、やがてデータアップされることになってしまえば、人間の評価軸はスペックだけとなり、一つでも上位の人間が下位の人間を露骨にさげすむ冷酷な社会が到来する」
(NHK BS放送『欲望の資本主義 2019』)
そして、そういう方向に向かい始めた中国を、岩井氏は「監視経済社会」という言葉を使って警戒している。
それは、イギリスの小説家ジャージ・オーウェル(写真下)が1949年に書いた近未来小説『1984年』の世界にほからないという。
オーウェルは、その小説で、民衆が高度な監視社会に苦しむディストピア(暗黒の理想郷)を描いたが、今の中国はまっしぐらにそこに向かっているとも。

5Gによる「スマートシティ」は
ディストピア社会につながっていくのか?
このような “ディストピア” 的な世界がすでに実現されようとしている。
それが、ファーウェイが中国の深圳に開発している世界初の超高度電子都市「スマートシティ」である。
この町では、人の流れや車の流れなど、刻一刻と変化する町の状況をすべて監視スクリーンでフォローできるようになっている。
その “秘密兵器” となっているのが、5Gのような新しい通信インフラだ。
これは、従来の4Gレベルのものと比べると、通信速度が10倍。監視カメラが接続できる数も10倍となり、AI の顔認証システムと結合することによって、町行く人々の行動が瞬時に把握できるような機能を持つことになる。

ファーウェイ側は、こういうシステムを強化することで「犯罪防止と治安強化」に貢献するというが、そのデータが警察に回った場合、中国共産党に対して批判する人々を簡単にチェックすることが可能となる。
つまり、政府にとって都合の悪い人間をどんどん取り締まれるような社会を実現するための “装置” だともいえる。
もちろん、ファーウェイの梁華(リャン・ファー 写真下)会長は、
「自分たちのシステムが中国共産党からデータを提供するように言われたことは一度もないし、今後も政府の要請に応じるつもりはない」
と事あるごとに説明しているが、アメリカ政府などはその発言そのものを信じてはいない。

現在、この「スマートシティ」構想は、ドイツのデュイスブルグという都市を巻き込もうとしている。
同市の市長は、この中国テクノロジーを活用することによって、市の産業を立て直し、経済的繁栄を実現しようと積極的に動いている。
もちろん、「スマートシティ」というアイデアが、経済効率の飛躍的アップを図ることは間違いないだろう。
だから、この構想を進めたいと考える国や企業のトップも非常に多い。
しかし、中国製の「スマートシティ」が、今の中国政府の思惑と合致していることだけは間違いない。
というのは、現在のところ、このデュイスブルグという町が、習近平政権が進めている “一帯一路” の西の最終拠点となっているからだ。
一帯一路というのは、鉄道、港、道路などの交通インフラの整備が主流となるが、中国政府は、その線に沿う形で、通信網の整備も進めている。
それが5Gを使った「スマートシティ」の建設で、中国はこの通信網整備を「デジタル・シルクロード」と呼んでいる。
(以上 NHKスペシャルより)

根本にある儒家思想が
西欧的価値観を排除する
話を最初に戻す。
なぜ中国は、20世紀に西側諸国が掲げた「自由」「民主主義」「人権」などという価値観を何の未練もなく捨てられるのか?
中国には、最初からそういう思想がなかったからだ。
西側諸国の価値観というのは、ここ200年ぐらいの間に形成されてきたもので、4,000年に渡る中国の歴史に照らし合わせてみると、まだ底が浅い。
「底が浅い」かぎり、中国人は、そのような考え方を普遍的な価値観として認めるわけにはいかない。
習近平政権の指導部の人たちは、みなそういうふうに考えているはずだ。
ヨーロッパ人たちが20世紀になってようやく価値を認め始めた「自由」「民衆主義」「人権」などというのは、すべて狭い大陸の小国同士で争っていたヨーロッパ人の考え方で、4,000年以上も昔から広大な領土を統一するために知恵を絞ってきた中国人には通用しない。
そういう彼らの考え方の背景には、儒家の思想がある。
儒家とは、紀元前552年に生まれた孔子の教えを守る人たちのことであり、その根本精神は、
「民の幸せは安定した国家運営だけが実現する」
と考えるところにある。
すなわち、儒家の教えでは、個人に「自由」とか「人権」などを与えるよりも、争いのない統一国家を実現することの方が優先される。
そこまで徹底しなければ、民族も言語も宗教も異なる広大な中国大陸を統一することは不可能だったろう。
習近平政権というのは、中華帝国を守るために腐心してきた歴代の皇帝がやってきたことを、ただ忠実に履行しているだけのことかもしれない。
だから、中国の “膨張政策” というのは、万里の長城を築いて北の蛮族の侵入を阻止したような、彼らの“防衛政策” にすぎないのかもしれない。