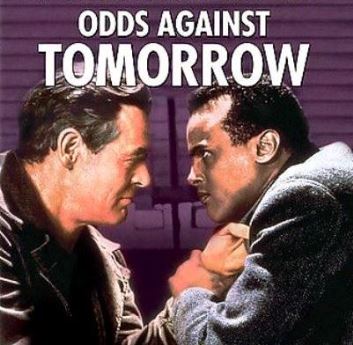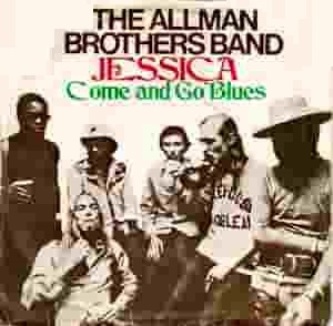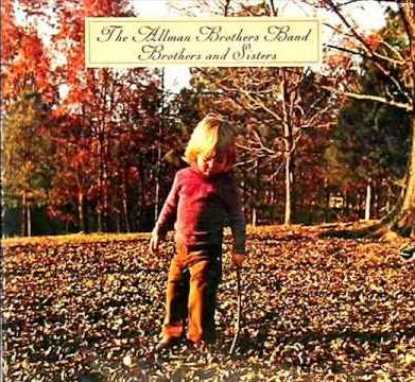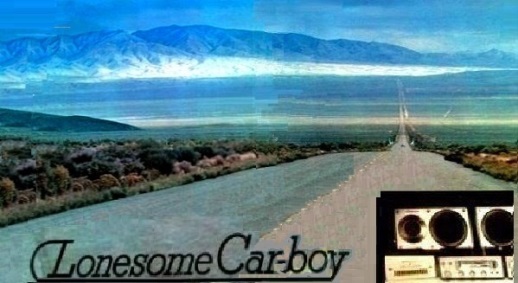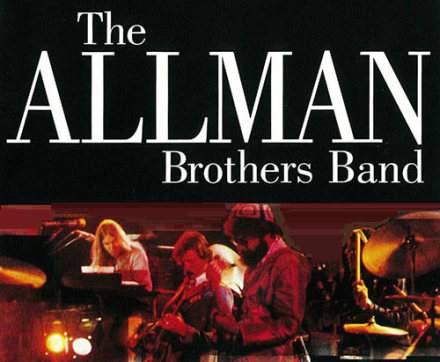つげ義春は、“夏の漫画家” である。
彼の重要な作品、もしくは、作品の中の重要な部分には、必ず「夏」の気配が深く刻印されている。
もちろん彼は、夏ばかりを作品の “舞台” として選んでいるわけではない。
木枯らしの吹く晩秋を描くこともあれば、粉雪の舞い散る冬を描くこともある。
しかし、作品世界を構成するキーとなる箇所には、必ず夏のべったりとした匂いが立ち込めている。
たとえば、つげ義春の作品が、多くの読者を獲得し始めた頃の代表作のひとつ『紅い花』。
釣り人である主人公が、山中のさびれた土産物屋で店番をする不思議な少女と出会う話は、むんむんとむせ返るような盛夏の中で繰り広げられる。

少女は初潮を迎えようとしている。
そのときの少女を襲う身体が重くなるようなけだるさ。
まさに、サナギ(少女)が蝶(女)に生まれ変わる前の不安定な状態そのものが、「夏の空気」の形を取ってねっとりと表現されている。
つげ義春の描く夏は、いつも時間が止まっている。
万物が狂おしく生命を謳歌する盛夏であっても、そこには奇妙な静寂が辺りを領している。
彼の描く夏には、誰にも埋めることのできない白っぽい穴が、ぽっかりと空いている。
たとえば、自分の見た夢をモチーフにして描いたといわれる『夢の散歩』。
▼『夢の散歩』(1972年)

道路も、並木の彼方に広がるはずの遠景も大胆に省略され、おそろしくシンプルな構成になっている。コマのいちばん中核を占めるスペースには何も描かれていない。
この白さが、この世のすべての「影」を「熱」で溶かしてしまうような、夏の陽のまぶしさを表現している。
つげ義春の描く、夏は、けっして生命力が燃え盛る能動的な季節ではない。
むしろ、生命が生気を失って、けだるさに包まれるアンニュイの季節だ。
そこでは、夏の陽射しに射すくめられるように、周りのものが動きを失い、物音が絶え、「死」にも近い「眠り」が忍び寄ってくる。
▼『散歩の日々』(1984年)

動きが止まるから、遠くにわき起こる入道雲に視線が吸い寄せられ、音が途絶えるから「チリン」と鳴る風鈴の音や、「ミーンミーン」と鳴くセミの声だけが際立つ。
そのとき、「夏」は、単なる四季のなかの1シーズンという役割を超えて、別の世界へ通じる「扉」に変貌している。
夏が旅立ちにふさわしい季節であるのは、人の魂が「夏の扉」を開いて地上から離れるからだ。
そのことを象徴的に語った作品が、つげ義春の『海辺の叙景』(1967年)である。
舞台は、夏の海水浴場。
享楽的に過ごす海水浴客たちに対して、ぽつんと距離を置くように、一人の青年が砂浜に座っている。
彼は、「日陰のもやしみたいだから、黒くなれ」と母親に誘われて、夏の海にしぶしぶやってきた男だ。

その場違いな雰囲気だけで、彼の「社会」に対するスタンスのようなものが浮かび上がってくる。
シャイなわけでもなく、人間嫌いなわけでもないのに、なぜか他者とのつながりを器用に結べない青年の孤独が、その表情にも、海辺に座るたたずまいからも伝わってくる。
青年はふとしたきっかけで、ショートヘアの美少女と口をきくようになる。
当初、無邪気にボーイフレンドたちと海を楽しむ “当世風” の女でしかないように見えた美少女が、実は青年と同じように、どこか鬱屈した心を持てあます孤独な人間であることを彼は知る。

砂浜を離れて、付近を散歩する二人の心の距離が、次第に近づいていく。
しかし、それは「恋」の形を取らない。
二人の心は、お互いに傷つくことを恐れるように、「恋」の周辺を手探りで探りあうだけなのだ。
なぜなのか。
二人の間に、のっぴきならない「運命」が待ち受けていることを、お互いに予感したからだとしか、言いようがない。
散歩の途中で、断崖絶壁を見下ろすシーンがある。
眼下に、禍々しい(まがまがしい)姿をさらす岩場が広がる。
それは、甘い恋の予感にときめく男女が見る風景としては、あまりにも恐ろしすぎる。
黒々としたベタで塗られた岩肌は、まるで二人を襲う巨大な獣の「足」のように見える。

青年は、「この辺りでは、水死した土左衛門がよく上がる」と少女に話す。
また、遠くの岬を指し、
「あの岬の下はタコの巣でね、無数のタコに襲われたら、たちまち骨にされてしまうんだ」
と語る。
少女は答える。
「信じられないわ。タコって可愛い感じなのに」
それに対して、
「本当はドウモウなんです。あの鋭いクチバシを見ればわかる」
と、青年は返す。
すでに、「死」のコノテーションが、二人の会話の中に散りばめられている。
散歩を終えた別れぎわに、
「あしたも来る?」
と、少女は尋ねる。
「うん。たぶんお昼すぎに」
「じゃあ …… 」
しかし、翌日は一転して雨。
小雨にけぶる海辺には海水浴客の姿もなく、海辺の貸しボート屋の軒先に律儀に座って少女を待つ青年。
やや遅れて、自分でデザインしたというビキニの水着を身にまとって現れる少女。
「勇気を出して着てきたの」
と、彼女はいう。
「すごくきれいだよ、すごく … 」
少女と同じくらいの勇気を出して、青年はそうほめる。
恋愛ドラマとしてならば、ここから一気に二人の心が高ぶっていくシーンが展開するはずだ。
事実、そういう展開になる。
なのに、最後のコマで、読者は言いようのない “宙ぶらりん” の状態に追い込まれる。
少女に、泳ぎの上手さをほめられた青年は、さらにその印象をダメ押しするかのように、一人で沖を目指して泳ぎ始める。
最後のコマ。

見開き2ページを使った大コマに描かれているのは、水平線を重く閉ざす雲と、降りしきる雨と、猛々しく牙をむいた波と、そして、その波に今にも飲み込まれそうな小さな青年の背中なのだ。
彼は、岸辺に戻る気があるのだろうか?
ふと、そんな懸念すら催させるような、不思議な終わり方だ。
「夏の扉」を開けて、彼は地上から別世界へ旅立った。
そんな思いを払拭しきれない。
そう思うと、青年に向かって、
「あなたすてきよ」
と、ささやく少女のつぶやきは、別れいく青年に対する餞別(せんべつ)の言葉のようにも響く。
すでに発表直後から、このラストを「青年の水死」に結びつける解釈も無数に存在した。
しかし、作者は必ずしもそのように描いていない。
「解釈」を、作品の外に放り出したのだ。
これは、夏という季節が、ひとつの「謎」をはらんだ季節であることを見事に描ききった漫画であると思う。
もちろん、「謎」という大げさな形をとったものではないのかもしれない。
“肌触り” としか言いようのないもの。
世間一般でいう「感動」を拒否するような、ザラザラした違和感。
しかし、その「違和感」こそが、この漫画に独特のリリシズム(叙情性)を与えている。
優れた作品は、そのラストシーンの向こう側に、それまで見えてこなかった世界が広がっていることを暗示する。
ミステリーのようなエンターティメントにおいても、謎が解き明かされ、お話としてはそこで終わりながらも、なおも薄ぼんやりとした巨大な謎が隠されているような感触を残すものがある。
読み終わった後もずっと気になる作品というのは、実は、90%のカタルシスの中に、10%ほど不透明なものが残ったようなものである場合が多い。
つまり、ひとつの「終わり」が、別の「始まり」を暗示させるようなもの。
おそらく、われわれが「余韻」という言葉で表現しようとしているものは、物語が終わったところからひっそりと始まる「別の物語の予感」のことである。