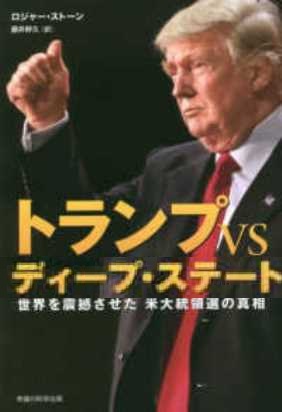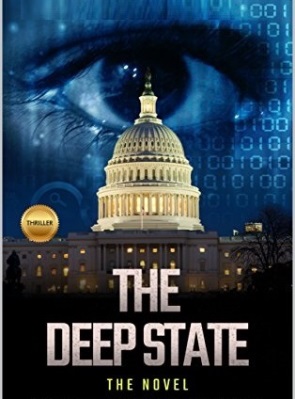庄野潤三の短編集『プールサイド小景・静物』(新潮文庫)を買った。
収録されていた七つの短編にはそれぞれ独特の空気があって、どれも不思議な気分にさせられた。

どの作品も、昭和25年(1950年)から昭和35年(1960年)までの間に書かれたものである。
芥川賞をとった『プールサイド小景』からすでに68年経つことになる。
しかし、読んでみると古びていない。
特に、『舞踏』と『プールサイド小景』などは、今のテレビ局が単発ドラマの原作として使っても、十分に通用するような話だ。
この本には、ほかに『相客』、『五人の男』、『蟹』、『静物』といった同時代の作品群が収録されているが、基本的には、どの話も、一般庶民のさりげない交流を描いた作品といっていい。
なのに、みな、どこか “落ち着かない” 。
そこはかとない “不穏な” 空気が漂ってくるのだ。
その中でも一番奇妙な味わいを持つのは、本の表題の一つとして掲げられている『静物』である。
この作品は、村上春樹が『若い読者のための短編小説案内』でも採り上げたことがあるので、それに触発されて、にわかに最近の若者にも読まれるようになったと聞く。
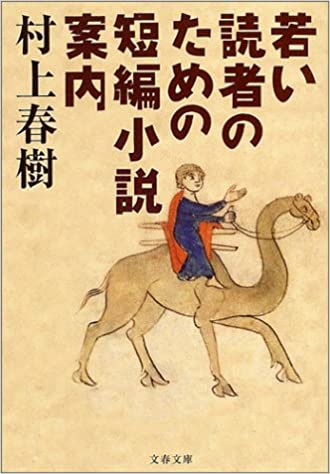
『静物』を読んでみると、確かに、ある意味で村上春樹好みの作品という感じもする。
主な登場人物は、父親、母親、そして女の子と2人の男の子である。
その家族の中で繰り広げられる日常生活の一コマ一コマが、何の脈絡もないまま並列につながっているだけの作品なのだ。
しかし、その一コマ一コマの “切れ目” に、何かが潜んでいる。
たとえば最初の章は、子供たちが、父親にせがんで釣り堀に連れていってもらい、意気込んで釣糸を垂れるのだが、何も釣れず、最後に父親が小さな金魚を一匹だけ釣って家に帰るところで、プツッと終わる。
事件が起こるわけでもなく、しゃれたオチが用意されているわけでもない。
なのに、この作品全体から、うっすらと不思議な感覚が立ち昇ってくる。
常に、文字として書き込まれていない何かがここには居座っている。
「何も起こらない」ことは、こんなにも不気味なものなのか?
そう思わせる何かが、この小説にはある。
その正体のひとつは、簡単に探し出せる。
家族のなかの、夫と妻との間にときおり忍び込んで来る「すきま風」だ。
ある晩、父親はそばで寝ている妻のことを、ふとこう考える。
「おれの横にこちらを向いて眠っている女 …… これが自分と結婚した女だ。15年間、いつもこの女と寝ているのだな。同じ寝床で、毎晩」
結婚したどの夫にも必ず訪れる、ごくありきたりの感慨かもしれない。
しかし、この覚めた夫の観察は、どこか異様である。
15年一緒に寝ているはずの妻に対し、ベッドのなかで見知らぬ女を見つけたときのような冷たさが文章から漂ってくる。
またある日、夫は家の中で昼寝しているときに、「女のすすり泣き」を耳にする。
妙だなと思って、台所を覗いてみると、妻はほうれん草を洗っていた。
「何か音がしなかったか?」
と妻に尋ねる。
「いいえ、何か聞こえました?」
と妻は晴れやかな顔をこちらに向けた、というのである。
結局、夫には「すすり泣き」の犯人がいまだに分からない。
場面はそこで変わり、話は子供たちのドーナツ作りに移っていく。
しかし、読者には分かってしまう。
たぶん、この夫は、かつて妻をすすり泣かせるようなことをしてしまったのだ。
読者にそう思わせる何かが、ここでは暗示されている。
でもそれが何であるか、作者は語らない。
多くの人が、この『静物』にときおり顔を出す「不安の徴候」に注目した。
そして、その「不安の徴候」こそが、この牧歌的で微温的な小説をピリッと引き締めるタガになっていると指摘した。
しかし、この『静物』という小説は、夫と妻の関係が明らかになれば、作品全体を貫く奇妙な味わいの秘密が解けるのかというと、そうではない。
夫の心理状態がどうであれ、妻の対応が何であれ、それとは関係ないところで、不思議なものが迫り出してくる。
その不思議なものを探る前に、以下の場面を見てみたい。
ある日父親は、男の子に、イカダ流しをしていた “川の先生” の話をする。
「川の先生は、川のことにかけては人とは比べものにならない名人で、川に魚が何匹いて、どっちの方向を向いて、何をしているということまできっちり言い当てる。
その “川の先生” が、『あとひとつ』というと、もうその川にはあと一匹しか魚がいないということなんだ」
それを聞いて、男の子は、話してくれた自分の父親に、「すごい!」と言う。
その話のついでに、父親は釣りをしていると必ず現れてくるキツネの話をする。
キツネはカゴに入った釣った魚を狙っていて、石を投げても、ヒョコヒョコと避けるだけで立ち去らない。
そして、油断をしていると、カゴをくわえて、すーっと走り去る。
聞いている男の子は「あーあ」とがっかりした声を出す。
「学校の花壇を掘っていたら、土の中からおけらが一匹出てきたの」
と、女の子が父親に話す。
「そのおけらはね、誰それさんの脳みそ、どーのくらい? って聞くと、びっくりして前足を広げるの」
そういって、女の子は両方の手でその幅を示す。
「そのおけらの前足の幅でね、みんなの脳みその大きさが分かるの」
男の子がボール箱の中に入れておいた蓑虫(みのむし)がある日いなくなる。
子供は、蓑虫を庭の木からつまみあげ、裸にして、木の葉っぱや紙切れと一緒に箱の中に入れ、巣をこしらえる様子を観察するつもりでいたのだ。
その蓑虫がどこかに姿を消す。
しばらくすると、蓑虫はいつのまにか子供の勉強部屋に巣を作って収まっている。
父親は、戸外に巣を作るはずの蓑虫が家の中に巣を作っている様子を見て、不思議な気持ちになる。
これらの話に、不気味な兆候というものは何一つない。
なのに、読んでいると、文字に書かれたもの以外の気配がそおっと降りてくる。
それはいったい何なのだろう。
一言でいうと、「自然」である。
この小説では、冒頭の金魚釣りから始まり、必ず同じ道をたどろうとするイノシシの話、あくまでも前へ前へと進むアユの話など、父と子供たちの会話に必ず「自然」が登場する。
テレビゲームも携帯電話もない昭和35年。
子供たちの遊びのフィールドがアウトドアだったことは分かる。
しかし、父親と子供たちの対話の中で、これほど自然をテーマにした話が繰り返されるとなると、庄野潤三が、「自然」という言葉に、なにがしかの意図を込めたことを感じないわけにはいかなくなる。
たぶん、庄野潤三は “自然” の持つ「超越性」を、この作品の中に導入したかったのだ。
人間が、可能な限りの人智を奮っても制御できないもの。
人間のつくり出す秩序を軽々と超えて、人間などには関わることのできない大きな秩序を形成しているもの。
父親は、それを「自然」という言葉に仮託して子どもたち( … つまりは読者)に伝えようとしたのだ。
それが、この作品の底に流れる “不気味なもの” の正体だ。
この『静物』という作品は、舌を巻くほど見事な描写力を誇っている小説である。
特に、子供たちが見せる無邪気な会話や仕草。
それを、これほどまで克明に写し取った作者の技量は、並大抵のものではない。
しかし、そのようにして獲得されたリアリティは、逆に「リアリズムでは獲得できない世界」があることも、地面に落ちた影のように映し出してしまう。
その一つが、「消えた蓑虫が、ある日こっそりと勉強部屋に移動して作ってしまった巣」である。
これは、実はとんでもない “謎” を秘めた話なのだが、この小説では、それがまったく「謎」として描かれていないところが怖い。
つまり、「消えた蓑虫」というのは、日常生活の中にせり出してきた異形のパワーとしての「自然」の比喩である。
それは、子どもたちには分かるが、大人には分からないものだ。
村上春樹は『若い読者のための短編小説案内』の中で、ここに登場する子供たちを、作者の「イノセンス(無垢)」への憧憬が表現されたものとして捉える視点を披露した。
そのイノセンスこそ、子供たちが無意識に備えている「自然」への親和性と解釈することもできる。
庄野潤三がこれを書いた昭和35年(1960年)という時代は、まだ都会生活を送る人々の間ですらも、自然をテーマに語るときの素材が豊富に溢れていたのだ。
しかし、今ここで描かれたような自然と接することができるのは、人里離れた山奥にでも行かなければ無理になった。
だからこそ、『静物』という作品が、不思議な光芒を放つように感じられるのは、逆に今の時代かもしれない。