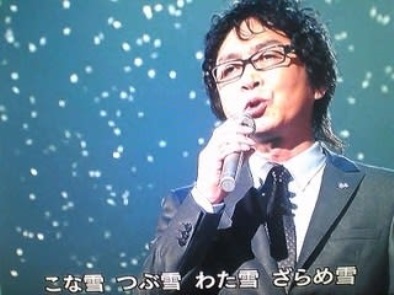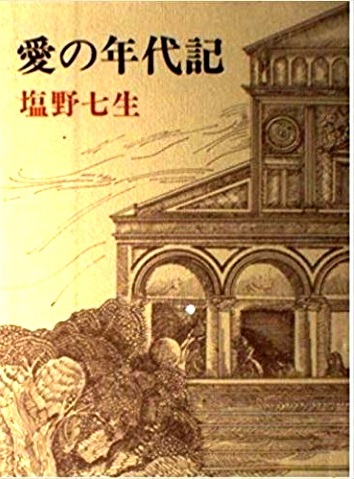- 戦争アクション映画:原題:Battle of the Bulge1965年|アメリカ映画|カラー|175分|画面比:2.20:1(70 mm)スタッフ監督:ケン・アナキン製作:ミルトン・スパーリング、フィリップ・ヨーダン脚本:フィリップ・ヨーダン、ミルトン・スパーリング、ジョ.. 続きを読む
映画 バルジ大作戦 - allcinema www.allcinema.net
- このキーワードを含むブログを見る
映画批評
男の子はこんなシーンに泣く
映画を観ていると、ときどき泣けるシーンというのが出てくる。
涙腺がゆるんで、ジワッとくる場面。
それって、自分の場合は戦争映画とか、アクション映画に多い。
ドイツ将校がこんなにカッコいいとは!
最近、泣いたのは、『バルジ大作戦』。
第二次大戦末期のヨーロッパ西部で行われた「ドイツ軍の戦車部隊」と「連合国軍の歩兵部隊」の戦いを描いた戦争アクションもの。

この映画が1965年に日本で公開されたとき、自分は西部劇や戦争映画の好きな中学生であったが、この映画だけは見逃していた。
それを、50年経って、ようやくテレビのBS放送で観たのだ。
1960年代というのは、第二次大戦を勝ち抜いたアメリカやイギリスの戦勝気分がまだ濃厚に残っていた時代で、宿敵ドイツを倒した連合国賛美の映画がたくさん作られていた。
『ナバロンの要塞』 (1961年)
『史上最大の作戦』 (1962年)
『大脱走』 (1963年)
『大列車作戦』 (1964年)
『バルジ大作戦』 (1965年)
『特攻大作戦』 (1967年)
『荒鷲の要塞』 (1968年)
『パットン大戦車軍団』 (1970年)
『ロンメル軍団を叩け』 (1971年)
これらの作品ではドイツ軍は悪役だから、映画に登場するドイツ軍将校たちのキャラクターはたいてい冷酷で、無慈悲で、傲慢(もしくはマヌケ)。
映画の途中で殺されちゃうと、観客が「やったぁ !」と心の中で叫んでしまうような役柄をあてがわれていた。
しかし、『バルジ大作戦』に登場するドイツ軍将校のヘスラー大佐という人物だけは違っていた。
スーパーヒーロー「ヘスラー大佐」
もちろん、基本的にはこれまでの悪役ドイツ将校ならではの類型が忠実に守られている。
ところが、ヘスラー大佐の場合は、
ドイツ将校の冷酷さが、「クール」に見え、
傲慢さが、「プロとしてのプライド」に感じられ、
無慈悲さが、「職務への厳しさ」に思えてくる。
そして、「ユーモアも解さないような人間味に乏しい」キャラクターが、なにやら「感情に左右されない知性の人」というように、すべてがカッコいい方向にバイアスがかかっていく。

ヘスラーを演じるのは、イギリスの俳優ロバート・ショウ(1927~1978年)。
イギリス人なんだけど、髪をブロンドにして眉の色を薄くすると、ドイツ人のエリート階級に見えてくるから不思議。

上の写真なんか、いかにも名門出身のドイツ将校という雰囲気だが、下の写真だと、たいした教育も受けていない下層階級のおっちゃんという表情になっていて、同じ人だとは思えない。

上は、『ジョーズ』(スピルバーグ監督 1975年)のサム・クイント船長に扮したロバート・ショウ。
サメ退治に長けた荒くれ漁師として登場した彼は、『ジョーズ』という映画の実質的な主役であった。
で、このロバート・ショウ。
『ジョーズ』公開の10年前に作られた『バルジ大作戦』においても、連合国側の主役級スターたち … すなわち、ヘンリー・フォンダ、ロバート・ライアン、チャールズ・ブロンソンなどを置き去りにして、実質的な主役に収まっている。
アメリカ映画なんだから、アメリカ軍俳優たちの方がカッコよく見えなければならないはずなのに、ドイツ将校のロバート・ショウの方がカッコよく見えてしまうのは、それって、脚本とか演出のせい?
それとも、ロバート・ショウそのものが持っている存在感のせい?
男の理想像
とにかく、彼の演じるヘスラー大佐は、ともすれば現在の我々が見失いがちな「男」の一つの理想像を見せてくれる。
それは、けっして、今の男たちから見て心地よいものではないし、女性たちから評価されそうなものでもないかもしれない。
だが、無類にカッコいい。
この映画で描かれたヘスラー大佐は、徹底して「理詰めの人」であり、「計算の人」であり、「人間の曖昧さよりも機械の正確さ」を好み、「人間の優しさをあえて踏みにじることで、自分の退路を断ち、無人の荒野を目指すような男」なのだ。
彼は、自分の目で見たものしか信じない。
だから彼は、会議室から視察にきたナチスの上官に対しては、言葉を変え、表情を変え、「戦争は会議室で起こっているのではない ! 現場で起こっているのだ !」と熱弁を奮う。
もちろん、それは映画だからこそ可能なことで、戦場で上官の命令をくつがえす現場の指揮官がいるわけはないのだが、ロバート・ショウ演じるヘスラー大佐を観ていると、実際にこういう将校がドイツ陣営にいたような気持ちになってくる。
映画の3分の1が終わるころ、ついに印象的なシーンが登場する。
ドイツ軍の西部戦線司令室がある地下壕のシーンだ。
この秘密の地下基地で、ヘスラー大佐は、新しく戦車軍団に編入されることになった新兵たちを閲兵する。
彼は、新兵たちの顔を一目見て、不機嫌な表情になる。
「Boys … too many boys」(ガキばかりじゃないか !)
とつぶやいて、彼は、新兵たちに冷たい目を向ける。

戦車隊の指揮を執るヘスラーからすれば、戦車というマシンが最初から「完成された武器」であるのに対し、戦場も知らない新兵たちは「未完成な武器」でしかない。

この時代、ドイツ機甲師団の「ティーゲル戦車」というのは、第二次世界大戦中に開発された兵器のなかでは最高の技術水準を誇った兵器だった。
その乗り手ともなれば、ドイツ陸軍の中でもエリート中のエリート。兵士のなかでも、ずば抜けて頭脳優秀な者でなければティーゲル戦車隊には採用されなかった。
だから、新兵といえども戦車隊に配属されるかぎりは、当時のドイツ陸軍の最精鋭ともいえるのだが、それでも「人間の曖昧さ」を嫌い、「機械の正確さ」を偏愛するヘスラーにとっては、黙りこくっている新兵たちの実力が疑わしくて仕方がない。
戦車隊指揮官ヘスラーと新兵たちの間に、気まずい沈黙が生まれる。
そのとき、指揮官の心を読んだのか、沈黙を守っていた新兵のうちの一人が、突然「戦車兵の唄(パンツァー・リート)を唄い始める。
それに合わせ、新兵たちが次々と合唱に加わる。
♪ 我らが戦車、風を切り !

♪ 嵐でも、雪でも、日の光さすときも、
うだるような昼、凍えるような夜、
顔がほこりにまみれようと、我らが心はほがらかに
我らが戦車、風を切り、突き進む。

新兵たちの合唱を聞くヘスラーの表情が次第に変わっていく。
やがて、ヘスラーは自分の身辺の世話をしてくれるコンラート伍長にも「歌え」と命令し、最後は自分自身も新兵たちの合唱に合わせ、「戦車兵の唄」を高らかに唄いだす。

▼ 『バルジ大作戦』 戦車兵の唄が流れるシーン
機械を偏愛する男が
ついに「人間」に心を開く
このシーンが、なぜこれほど感動的なのか?
それは、これまで「人間」を「機械」としてしか評価してこなかったヘスラーが、はじめて目の前に「人間」がいると知ったシーンだからだ。
確かに、人間は、機械のようにいつも同じ正確さを持って作動するわけではない。鋼鉄のようにタフでもなければ、砲火のような破壊力も持たない。
しかし、人間は「意気に感じる生き物」である。
仲間を助けるために、自分の身を犠牲にさらすという “狂気” すら持ち合わせている。
ヘスラーは、新兵たちの唄に、「人間の狂気」を感じたのだ。
すなわち、人間というのは、自分個人の弱さを「団結」という狂気で克服していく生き物だということを。
そういった意味で、まさにこれは戦争映画史に残る金字塔のようなシーンといっていいのだが、私はこのシーンで泣いたわけではない。
これは伏線に過ぎない。
ヘスラーの死に、男の子は涙

『バルジ大作戦』という映画は、やはりアメリカ映画だけあって、ドイツ将校のヘスラーの死を持って終わることになる。
大量のガソリンを浴び、アメリカ軍の十字砲火を浴びて、ヘスラーの乗るティーゲル戦車が炎上する。
すでに、車内の操縦兵も死傷。
瀕死のヘスラーは、戦車の床に這いずりながら操縦席に移動し、壊れかけている戦車を操りながら、必死に死地からの脱出を試みる。
しかし、燃え始めているキャタピラーが、もう斜面をグリップする力を失っている。
それでも、ヘスラーは血で濡れた手で戦車のハンドルを握りしめ、最後の脱出に希望をつなぐ。
そのとき、歯を食いしばった彼の口から、自分自身を鼓舞する歌が流れ始めるのだ。
♪ うだるような昼、凍えるような夜、
顔がほこりにまみれようと、我らが心はほがらかに
我らが戦車、風を切り、突き進む。
男の子は、ここで泣く。
勇壮な響きを持つ「戦車兵の唄(パンツァー・リート)」が、もうここではヘスラーへの鎮魂歌になることが分るからだ。
そして、“予定通り” ヘスラー車はガソリンの洪水に足を取られ、迫りくる劫火を防ぐこともかなわず大爆発。
連合軍側にとっては、「めでたし、めでたし」のうちに、エンドマークが降りてくる。
『スターリングラード』で
異彩を放ったエド・ハリス
というわけで、死んでしまったドイツ将校がいかにカッコよかったか、ということを強く印象付けて、この映画は終わるわけだが、敵役のドイツ将校をカッコよく描いた映画がもう一つある。
第二次大戦下におけるドイツ軍とソ連軍の戦闘を描いた『スターリングラード』だ。
この『スターリングラード』という映画の特徴は、“団体戦” としての戦争ではなく、“個人競技” としてのスナイパー(狙撃兵)同士の駆け引きを描いたところにある。

主人公のソ連側のスナイパーを演じたのが、ジュード・ロウ。
その敵役となったのが、アメリカの名優エド・ハリスが演じるナチスの将校ケーニッヒ少佐(写真下)。

エド・ハリスに与えられた役柄は、定番通りの冷酷で無慈悲なナチス将校なのだが、これがまたなんともカッコいいんだわ。

高級将校が泥まみれのスナイパーに変身
観客が最初に見るのは、端正な軍服に身を包み、ドイツから来た専用列車の個室で優雅に金の吸い口のタバコをくゆらすケーニッヒ少佐。
たぶん、すぐに主人公に射殺されちゃう役なんだろうな … と思っていたら、戦地に着いた彼は、将校の軍服をいさぎよく脱ぎ捨て、敏捷に動ける戦闘服に着替えるやいなや、地を這い、木陰に身を潜めて、主人公のスナイパーを射殺するためのスナイパーとして暗躍し始める。
う~ん …… と、うなるほどの変身ぶりで、これまで映画を通して見てきたドイツ将校のイメージがまたひとつ変わった。
アメリカ人の感じるドイツ的なもの
なぜアメリカ映画は、カッコよいドイツ将校を奇跡的に描いてしまうのか。
たぶん、ドイツ的なるものにコンプレックスがあるのだろう。
では、アメリカ人の感じるドイツ的なものとは何か?
それは、「機械のように正確に作動する人間」である。
『スターリングラード』に出てくるケーニッヒ少佐は、自分自身が銃器と同化して、“マン=ガン系” ともいうべき合成人間になってしまったようなプロフェッショナルであった。

『バルジ大作戦』のヘスラー大佐は、機械工学的な視点でティーゲル戦車軍団の戦術を編み出すプロであった。
こういう “マン=マシン系” の人間像に、アメリカ人って弱いんだろうな … と思う。

ドイツ人もアメリカ人も、ともに合理的な民族であるが、アメリカの合理主義というのは、人間の “ダメさ加減” を補正する意味での合理主義である。
彼らは、人間の行う作業でマニュアル化できないものはないと思っている。
マニュアルというのは、未熟な者を使いこなすための技術である。
どんな従業員を雇っても、1時間後には即戦力となるような「マクドナルド」に代表されるファストフード産業は、こういうマニュアル文化の中からしか生まれて来ない。
狂気を秘めたドイツ的合理主義
それに対し、ドイツ的合理主義ってのは、最初から完璧なるものを求める。
そして、それがどこかで「狂気」に通じていることも分かっている。
合理的思考の中に「狂気」がまぎれ込むのではなく、彼らは、合理性をとことん突き詰めていくと、ある段階で突然白と黒が反転するように、そのまま狂気になることを知っている。
だから、ニーチェやフロイトやマルクスは、ドイツからしか生まれてこない。
そして、現代のドイツ人がナチスの所為を反省するのも、そこのところに由来する。
それは、そのままアメリカ的な文化と、ドイツ的な文化の違いになって表れてきているような気がする。