コロナ禍で「ステイホーム」が浸透したせいか、書店の売上げが伸びたという。
確かに、読書は、ある程度 “退屈な時間を持て余す” という気分に支えられるようなところがあるから、運動も外出も制限されたときのやるせない気分を紛らわせるには理想的な時間のつぶし方といえる。
私も、長い入院を経験したことがあるから、読書に助けられたという記憶を持っている。
4~5年ほど前、肺血栓症の手術を受けるために、1月、6月、7月、10月と、1年のうちに4回入院したことがあった。
長いときは2ヶ月近い入院を経験した。
じっくり本が読めた。
2016年に入院したとき、病院の売店で、村上春樹の『女のいない男たち』を買った。

この年も、村上春樹がノーベル文学賞を授与されるかどうかが、巷の話題となっていた。
しかし、春樹ファンには残念なことに、ノーベル文学賞はボブ・ディランのもとに去った。
私は、村上春樹の作品を適度に読んでいる方だと思うが、彼がノーベル文学賞に値するような作品を書いているのかどうかということに関しては、正直、よく分からない。
私のイメージでは、村上春樹という人は世界の文芸史に名を残す “大文豪” というようなタイプではなく、本来は、少数のごくセンスのいいファンたちがこっそり評価し合うような作家に思えるのだ。
そして、その方が、愛読者にとっては、かえって安心して「村上ファン」を名乗ることができるような気がする。

で、『女のいない男たち』。
六つの短編で構成されている。
そのどれもが、基本的に、女に振られたか、女に死なれたか、女に自分の思いをうまく伝えられなかった男たちの話になっている。
村上春樹は、なぜそのような男たちを取り上げる気になったのか。
もしかしたら彼は、これからは、男には恋愛が不可能な時代が来ると踏んだのではなかろうか。
つまり、男の恋心を受け入れてくれる女性が次第に少なくなりつつあると感じたのだ。
六つの短編において、主人公から去って行った女たちは、いずれも男と一緒に迎える “ハッピーエンド” を拒否する。
女たちは、他の男と不倫するにせよ、自殺するにせよ、いつの間にか姿を消すにせよ、みな男が用意したハッピーエンドの<外>に歩み去っていく。
そして、男たちは、女が去っていく理由も分からず、途方に暮れるか、いつまでも懊悩する。
それは、そのまま現代社会の男女関係をぞっているように思える。
なぜ、男たちにとって、これほど恋愛が難しい時代がやってきたのか。
結論を先にいえば、それは現代社会が、「男の恋愛文化」を失ったからである。
すなわち、恋愛からセンチメンタリズム(感傷的情緒)が失われたのだ。
これまでの古典的な男の恋愛観は、すべて女に対する男の片思いやら女に振られたときのセンチメンタリズムをベースに構成されてきた。
こういう言い方もできるだろうか。
センチメンタリズムが保証されていたからこそ、男たちは孤独な片思いやら辛い失恋に耐えられたのだと。
▼ 愛する女が去っていく姿を見つめる主人公 映画『カサブランカ』

つまり、それまでの男たちは、思いを遂げられない心の痛みをセンチメンタリズムで濾過(ろか)できたからこそ、傷をしのぐことができた。
そして、「失恋に耐えた」経験が、その男の滋養となり、次の恋愛に向き合う覚悟を準備した。
こうして、昭和の青年たちは、かろうじて恋愛対象と向き合うことができたのだ。
しかし、そのようなセンチな男文化が生き延びられたのは、せいぜい昭和50代までではなかろうか。
50年代の終わり頃は、男のセンチメンタリズムを強調した歌謡曲が、まさに最後の宴を謳歌するがごとく、歌謡曲のヒットチャートを席巻した。
『ルビーの指輪』(寺尾聰)
『もしもピアノが弾けたなら』(西田敏行)
『みちのくひとり旅』(山本譲二)
『帰ってこいよ』(松村和子)
『スローなブギにしてくれ』(南佳孝)
『サチコ』(ニックニューサ)
そのどれもが、恋を成就させることのできなかった男の自己憐憫を美化した歌である。
1960年代から1970年代の半ば頃までの歌謡曲は、藤圭子の演歌に代表されるような、「騙された女/捨てられた女」の世界だった。
しかし、1978年に杏里が『オリビアを聴きながら』を歌った頃から、男女の形勢が逆転し、80年代以降の歌謡曲は「泣く男」の世界となった。

いったい、そこで何が起こったのだろうか。
高度成長からバブルに向かっての一時期、日本はつかの間の “一億総中流社会” を実現する。
その時代に、男が会社勤めに出て、女が専業主婦として家事を切り盛りできるような社会が誕生した。
専業主婦というのは、女性の「無報酬労働」である。
つまり、女が無報酬で家事というシャドーワークに専念できるほど、日本の家庭は見かけ上の豊かさを維持することができたのだ。
この余裕が、男のセンチメンタリズムを育てた。
専業主婦たちは、会社勤めのような “社会” を経験せずに暮らせたから、男の身勝手な甘えの文化に無頓着でいられたのだ。
しかし、共稼ぎの時代が訪れ、外で働き始めた女性たちは、次第に男のセンチメンタリズムが許容できなくなっていった。
そのようなセンチメンタリズムは、男の自己完結的な自意識の産物だから、それ自体に生産性がない。
当然、バブル崩壊後に生まれてきたせちがらい世の中は、そういう情緒性のはびこる文化を許さなくなっていった。
1990年代になり、日本経済が津波に吞み込まれるように崩壊していくなかで、企業倒産が続出。男の安定した雇用が消滅していく過程で、男たちは、みな「女に振られた悲しさ」を歌や酒や旅でまぎらわすといった情緒的な方法で処理できなくなっていく。
村上文学とは、こういう時代が始まる直前に登場した文学である。
すなわち、男が女を失うときのセンチメンタリズムがまだ機能していた時代の最後の文学なのだ。

村上春樹が『風の歌を聴け』で群像新人賞を取ったのは1979年。
『1973年のピンボール』が芥川賞の候補になったのは1980年。
つまり、村上春樹の初期作品は、日本社会が男のセンチメンタリズムを許容していたぎりぎりの年に生まれている。
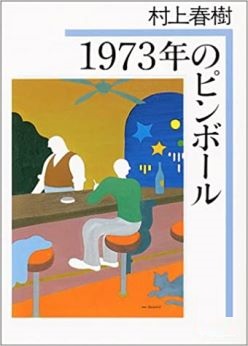
それらの作品に登場する “僕” と呼ばれる主人公たちは、女の理不尽な行動にも取り乱すことなく、ただ「やれやれ」とつぶやいて耐えている。
しかし、それは見かけ上の冷静さであって、彼らの本心を占めているのは女々しさである。
その女々しさが、あまりにも洗練された筆致で処理されるために、センチメンタリズムの上澄みが浄化され、そこにドライでクールな空気感が生まれたのだ。
それが、村上流 “喪失の文学” の正体である。
そう考えると、村上文学の構造というのは、案外シンプルである。
それほど奥行きのある世界ではない。
ただ、そう思わせないテクニックを村上春樹は持っていた。
それは、「肝心なことは描かない」というテクニックだ。
彼の小説作法を解き明かした名著のひとつに、『若い読者のための短編小説案内』があるが、そのなかで、彼はこんなことを書いている。
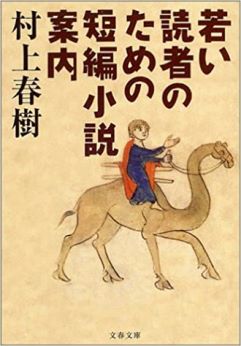
「優れた作家はいちばん大事なことは書かないのです。優れたパーカッショニストがいちばん大事な音は叩かないのと同じように」
まさに、これは、村上春樹の小説作法そのものを表現した言葉であり、彼の全作品がこの作法に則って作られているといっても過言ではない。
この『女のいない男たち』においても、その手法は貫かれている。
たとえば、『シェラザード』という短編では、施設に閉じ込められた主人公の男性のもとに、身の回りの世話をする女が一人通ってきて、冷蔵庫のなかに食材を詰め、退屈しのぎのために読む本を用意し、主人公を相手にルーティンワークのような情事をこなし、そのあと、ベッドに寝たまま魅惑的な話を披露して去っていく。
主人公にとって、その女の話の続きを聞くことが一番の楽しみになる。
しかし、ある日主人公は、その女性がもう姿を現わさないのではないかと予感に怯える。
もちろん女性の言動からその兆候を読み取ったわけではない。あくまでも、予感にすぎない。
でも、その予感は、主人公を茫洋と霧が立ち込めるような哀しさのなかに沈ませていく。
そこで、この短編はすとんと終わる。
けっきょく最後まで何も描かれない。
主人公がどのような施設に閉じ込められているのかも語られず、彼がなぜそこから抜け出ようとしないのかも説明されず、主人公のもとを訪れる女性の正体も明かされない。
実は、何も説明されないということが、ここでは “詩” になっているのだ。
この短編には「情感」だけがあって、「ロジック」がない。
つまり、物語自体が、壮大な “余韻” に包まれているのである。
何もかもがはっきりと描かれないからこそ、切ない。
村上春樹のセンチメンタリズムというのは、そういう形で提示される。
私はそれをとても心地よいと思うけれど、この先、この村上春樹的センチメンタリズムがどこまで読者に通用するのか、それはまったく分からない。
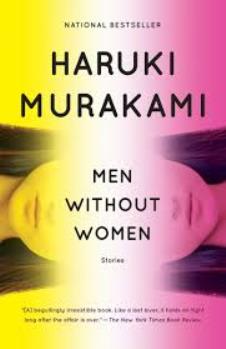
ただ、入院中の私は、この村上作品によってずいぶん癒された。
1ページを読み終えるごとに、その余韻を噛みしめるように、病室の窓から見える青空を眺めた。
村上春樹センチメンタリズムは、病室で独り取り残された老人の心にも寄り添ってくれた。