祝祭(ダイヤモンド)と死(灰)
『灰とダイヤモンド』という言葉から、今の人たちは何を想いうかべるのだろうか。
2013年に、ももいろクローバーZがリリースしたアルバムの中に、そういうタイトルの歌があるという。
1994年までさかのぼれば、日本のロックグループGLAY(↓)がインディーズの時代に出したアルバムにも『灰とダイヤモンド』という曲が入っているそうな。

さらに古い時代に遡行すれば、1985年に沢田研二が、やはり『灰とダイヤモンド』(↓)というタイトルで、44枚目のシングルレコードを発表したとか。

個々の歌がどのような内容を持つのか。また、なぜそのようなタイトルが付けられたのか、私は知らない。
ただ、なんとなく思うのだが、三つの曲を作ったそれぞれの人たちは、いずれも『灰とダイヤモンド』という言葉から何かのインスピレーションを拾ったのではないかという気がするのだ。
それは1958年に、ポーランドの映画監督アンジェイ・ワイダによってつくられた、あまりにも有名な映画のタイトルだからだ。
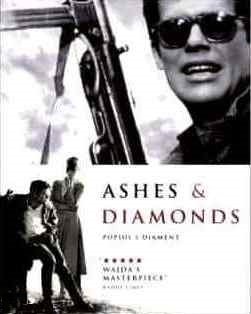
コロナウイルスの蔓延が強いる “巣ごもり状態” の日々から逃れるために、昔から気になっていた映画を発掘し、あらためてそれを観賞する時間をつくっている。
今回は、ポーランド映画を代表する傑作といわれる『灰とダイヤモンド』。
制作年は、1958年。
60年以上も前の作品となる。
もちろん、フィルムはモノクロ。
画質も音質も、今の映画の水準から比べると、けっして良いとはいえない。
だが、見始めると、一気に引き込まれた。
やはり、「名作」といわれる映画は、60年程度の “古さ” などまったく問題にしないようだ。
今の時代にも色あせないカッコいい映像
計算され尽くしたカメラアングル。
音楽と役者のセリフがスリリングにかみ合う音響効果。
登場人物たちの魅力的な表情。

もう、何から何まで新鮮 ‼
ここで展開されていたのは、むしろ現代映画がいまだ実現していない “未来的映像” だった。
もちろん、60年以上前の映画が、すべて新鮮に感じられるということはありえない。
そこには、やはりアンジェイ・ワイダという監督の天才的な才能が作用していたというべきだろう。
▼ アンジェイ・ワイダ監督

以下、この映画の時代背景を簡単に述べる。
舞台は1945年のポーランドのある地方都市。
その年の5月8日、それまでポーランドを占領していたナチス・ドイツが連合軍に降伏し、ポーランドはようやく解放されることになった。
しかし、ナチス・ドイツのくびきから自由になったポーランドには、すぐその次の支配者が迫っていた。
スターリン率いるソビエト連邦共産党である。
この時期、スターリンは、政敵や自国民への凄惨な粛清を繰り返しながら、ヒトラー以上の独裁政権を樹立しようとしていた。
スターリンの魔の手が迫る東欧

そのスターリンの政治介入を許したポーランドや東ドイツ、チェコスロバキア、ルーマニア、ユーゴスラビアなどの東欧諸国では、ソ連主導型の社会主義政府が次々と誕生し、イギリス、フランス、西ドイツなどの西側諸国と対立するようになった。
しかし、ポーランドには、ソ連が指導する社会主義政策を嫌い、自由主義政府を樹立したいと思うグループがいた。
彼らは、ソ連の息がかかったポーランド共産党の首脳陣を暗殺し、ソ連への抵抗運動を進めようとしていた。
ここまでが、この『灰とダイヤモンド』という映画の背景である。

共産党政府の検閲をどうくぐり抜けたのか?
映画の主人公は、“ポーランドのジェームス・ディーン” といわれたズビグニエフ・チブルスキーが演じるマチェク(写真上)。
その主人公に暗殺されるのが、ソ連で共産主義教育を受けてきた「ポーランド共産党員」のシチューカ(写真下)である。

今の時代を生きる我々が観ると、この映画は、共産主義の抑圧と戦う自由主義者を主人公にした “反体制ドラマ” に思える。
だが、この映画が作られたときの状況は、もう少し複雑だ。
監督のアンジェイ・ワイダがこの映画を企画した1950年代初頭。ポーランドの共産党政権は、自国の出版物や映像表現に厳しい検閲を施していた。
すなわち、少しでも共産党を批判するような文学・評論・映画があれば、たちどころに表現の修正を迫り、場合によって発表を断念させた。
だから、この映画のように、共産党政権を倒そうとする人間が主人公となるような作品は、当時のポーランドでは上映できるはずはなかったのだ。
では、アンジェイ・ワイダは、いったいどのようにして政府の検閲をくぐり抜けたのか。
主人公を変えたのである。
つまり、暗殺者のマチェクが主人公となる映画ではなく、見ようによっては、むしろ彼に殺されるシチューカ(写真下)の方こそ主人公だと解釈できる可能性を残したのだ。

すなわち、マチェクは、軽薄な “ちゃら男” として描かれ、一方のシチューカは、ポーランドの将来を真剣に考える “信念の政治家” というキャラクターを与えられた。
さらに、ワイダ監督は、シチューカを殺したマチェクが翌朝ポーランド政府軍に発見され、薄汚いゴミ捨て場で虫ケラのように殺されていくというエンディングを用意した。

このマチェクのみじめな死を確認した共産党の検閲者は、
「政府を転覆させようとしたテロリストの容赦ない末路を描いたこのシーンがあってこそ、この映画は共産党政府の正しさを実証する宣伝になる」
と手放しで喜んだと伝えられている。
しかし、映画を観た観客は、マチュクの死を、「共産党政府が自由を求める青年を惨殺するシーン」として解釈し、国家権力に対し、一層批判の目を向けるようになったといわれている。
この映画の “深さ” はどこから来るか?
ここまでの説明で、長い行数を使ってしまった。
しかし、ここからが本当にいいたいことである。
大事なのは、この映画には二つのテーマがあるということだ。
一つは、マチェクの視点に立って、ポーランド政府をコントロールしようとするソ連の支配体制を暴き出すこと。
そして、もう一つは、ポーランド共産党の検閲者を喜ばせたように、反体制派のテロリズムの空しさを説くこと。
この相反するテーマを一つの作品に融合させたからこそ、この映画は当時の映画の水準をはるかに超える “深さ” を獲得することになった。
作品の深さは、登場人物たちの内面の深さとなって表れる。
マチェクに狙われるシチューカは、筋金入りの共産党員として登場するが、実は、自分の息子がソ連に抵抗する反政府組織に入っているという悩みを抱えており、ポーランド人同士が二つの勢力に分かれて戦うことを防ぐことに奔走する男として描かれる。
ただシチューカ(↓)の場合は、新生ポーランドの建設に「ソ連の力を借りる」という方針を貫こうとしていただけなのである。

一方のマチェクは、ポーランド人同士の分裂に対する危機感をあまり持たない。
彼にとって「ソ連の支配と戦う」ことは、彼個人のロマンチックな英雄的行動にすぎない。
要するに、ナイーブ(無邪気)すぎるがゆえに、マチェクは人を殺すことにためらいを感じないのだ。

“ちゃら男” が知った本物の恋
そのマチェクが、なんとシチューカを暗殺する直前に、一人の女に恋してしまう。
行動を起こす前の時間つぶしのつもりで、彼はホテルの酒場女と火遊びを始めたのだ。
しかし、“ちゃら男” を気取っても、根が純真なマチェクは、自分の恋が真剣なものであること気づき、次第に自分に課せられた計画にとまどいを抱き始める。

とまどいは、「命の大切さ」を彼に教える。
彼は、シチューカの暗殺を企てれば、自分も殺されるリスクを負うということに、はじめて気づく。
恋人を持ったマチェクの心に、「死を恐れる心」が生まれる。
一方、マチェクの相手となった女は、ドイツとの戦いで家族や知り合いを失う数々の不幸を経験している。
だから、自分に言い寄ってきたマチェクが、すぐに自分のもとを去っていくことを本能的に察知する。
自分の使命と恋の板ばさみになったマチェクが、「悩みを打ち明けたい」と切り出しても、彼女は「悲しい話なら聞きたくない」とマチェクから顔をそむける。

悲劇に耐えた女は「物憂さ」を身につける
このときの哀しみとアンニュイ(物憂さ)に満ちた女の表情が美しい。
愛した者たちを戦争が次々と奪っていくという悲劇に耐えているうちに、
「去っていく者は引き止めても戻らない」
という諦めが彼女の心に住み着いてしまったのだ。
それが、女のアンニュイの正体である。
マチェクは、愛した女と一緒になることを考え、危険の伴うシチューカの暗殺計画を放棄したいと上官に願い出る。
しかし、マチェクの上官はそれを許さない。
仕方なく、マチェクは当初の計画どおりシチューカを付け狙う。
ホテルを出て歩き始めたシチューカを尾行し、追い越してから、振り向きざまに胸に銃弾を撃ち込む。
このとき、不思議なことが起こる。
撃たれたシチューカは、なんとマチェクから逃げるのではなく、逆に自分の “同志” を確認したかのように、マチェクの胸に飛び込んでいくのだ。
その体を放心したように支えるマチェク。
彼の顔にも、同志と抱擁を交わすような優しい表情が一瞬浮かぶ。
それは、
「いつの日かともに手を取り合い、喜びを分かち合おう」
と抱き合うポーランド人同士の “一瞬の連帯” であったかもしれない。
祭りのなかの「死」
二人の背後に、突然花火が上がる。
それは、ポーランドがナチス・ドイツから解放された5月8日を祝う記念の花火だった。

ポーランドの戦勝を祝うこの夜、町のホテルでは夜を徹したパーティーがずっと開かれている。
朝のまぶしい光が室内に射し込んできたというのに、パーティー会場のフロアでは、酔った男女の踊りが止まらない。

上機嫌になった紳士が、楽団に向かって叫ぶ。
「諸君、わが国の誇るショパンのポロネーズ(舞踏曲)を踊ろうではないか」
タバコの煙がたなびくダンスフロアに、調律の狂った楽器による不協和音に満ちたポロネーズが流れる。

狂騒のなかに忍び寄る “祭りの後の空虚さ” 。
画面から流れ出るのは、爛熟したデカダンス(退廃)とアンニュイ(物憂さ)。
記念すべき(?)新生ポーランド誕生の日が、なんとも気怠い疲労感に満ちたものであったかを匂わせながら、話は終盤に近づく。
パーティー会場の狂騒が続く同じ時間に、マチェクは瓦礫の上で息を引き取る。
「祝祭」と「死」が交差するなかで、米ソの2大強国が静かににらみ合う冷戦時代が幕を開ける。

『灰とダイヤモンド』とは、19世紀のポーランドの詩人ツィプリアン・ノルヴィットの詩の一節だという。
「すべてのものは、みな燃え尽きて灰となるが、それでも、その灰のなかに燦然と輝くダイヤモンドが残ることを祈る」
と歌っている、という。
