フランス革命で命を散らした “悲劇の王妃” として、マリー・アントワネットの名前を知らない人は、まずいないと思う。
▼ マリー・アントワネットの有名な肖像画

「民衆はパンが食べられなくて、みな困っています」
と侍従からの報告を受けたとき、
「それなら、ケーキを食べればいいのに」
と答えたというエピソードによって、贅沢ざんまいに明け暮れた “無知な王妃” という烙印を押されてしまったアントワネット。
しかし、近年の研究によると、アントワネットをめぐる上記のような逸話は、鬱屈したパリ市民の劣情を満足させるためのフェイクニュースだったということがはっきりしてきたという。
2020年の7月3日に、NHKのEテレで放映された『マリー・アントワネット最後の日々』というドキュメンタリー番組は、現代の歴史家や研究家が過去の記録を再検討して “アントワネット裁判” の真実に迫った面白い企画だった。

それによると、フランス革命をリードした指導者たちは、興奮したパリの市民たちの気持ちを鎮めるために、どうしても「王妃の死刑」を実現しなければならなくなり、そうとう苦労したらしい。
リーダーたちを困らせたのは、政治的興奮に酔ったフランスの民衆を納得させるほどのアントワネットの “悪行” がなかなか実証できなかったことだった。
そのため、彼女の不道徳性や傲慢さを訴えるために、ウソにまみれたフェイクニュースがたくさん捏造されという。
その過程で、民衆が求める「王妃の処刑」は、裁判の結果を待つまでもなく、筋書きが確定されていった。
実際のアントワネットの人物像はどうであったのか。
Wikipedia などを調べてみると、“ナイーブ(アホ)な貴族の典型” と冷笑される部分と、家族思いの優しい賢夫人という両面を持ち合わせていたように見える。

特に、捕らわれて牢獄に幽閉されるようになってから、彼女はようやく王妃としてのプライドと強さを獲得し、断頭台におもむくまで、凛々しい振舞いを貫き通したという。

しかし、身柄を拘束されるまでは、思うがままに生きた “わがままな王妃” という一面を見せることも多かった。
生まれたときから宮廷生活しか知らない王女だったのだから、庶民の生活感覚など理解できなかったのは仕方がない。
オーストリア王家からフランス王家のルイ16世に嫁いだアントワネットは、おそらく、この時代のヨーロッパで、もっとも豪奢で洗練された文化のなかに身を投じた女性だった。
彼女が暮らしたベルサイユ宮殿。
「太陽王」といわれたルイ14世が建てたその宮殿は、まさに、世界の富が流れ込んで来る場所だった。
17~18世紀のベルサイユ宮殿は、ディズニー映画の宮廷描写のモデルともなるような “夢の御殿” 。

そこでは夜毎王侯貴族たちによる華やかな舞踏会が繰り広げられ、その会場は、ファッションからジュエリー、食事に至るまで、ゴージャスの極みともいうべき世界中の贅沢品に埋め尽くされた。

ドイツの経済学者ヴェルナー・ゾンバルトは、『恋愛と贅沢と資本主義』(1912年)という本で、この時代のフランス宮廷で広まっていた豪華絢爛な物質的贅沢が「資本主義を用意した」という説を打ち立てた。
まさに、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の逆をいく主張である。
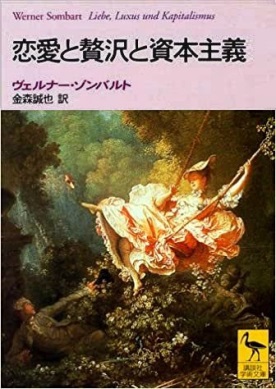
アカデミズムの世界では、ゾンバルトの “贅沢論” よりも、圧倒的にマックス・ウェーバーの『プロ倫』の方が、資本主義のメンタリティを解明するにふさわしいとされた。
生真面目なドイツ系プロテスタントの人々は、ストイックな倹約家の人間が資本主義の倫理観を築いたという説の方に、安心できるものを感じたのだ。
しかし、「贅沢なファッション」、「恋人(愛人)への豪華なプレゼント」というような要素が「資本主義を用意した」という説の方が、現代的であり、日本人にも理解しやすい。
私などは、ウェーバーの説よりも、このゾンバルトの説の方に魅力を感じる。
ゾンバルトがいうように、「贅沢に対する共感」が17世紀のフランス宮廷から生まれてきたというのは、ある意味、ベルサイユ宮殿の文化というのは、「女性を崇める文化」であったというべきかもしれない。
この時代、フランス宮廷のサロンを主宰したのは、みな女性であった。
ルイ15世の愛人であったポンパドゥール夫人(写真下)をはじめ、夜毎のパーティーを格調高いものに演出したのは、すべて国王や有力貴族の愛妾たちであった。

宮廷の男たちは、それぞれお気に入りの女性の心を射止めるために、カネに糸目をつけず、世界中の高級品を買いあさった。
(そこで実現した恋愛は、ほとんど不倫であった)
そのフランス宮廷で、ルイ14世の治世が終わったあたりから生まれてきた芸術様式を「ロココ」といった。
ロココとは優美、洒脱、繊細というエレガントな部分と、退廃、倦怠というアンニュイな部分が交じり合った独特の文化で、絵画にせよ、工芸品にせよ、美しいが砂上の楼閣のような、危うさを秘めていた。
そこが、ロココの魅力でもある。

▼ 典型的なロココ風デザインの室内

ロココが登場するまでの芸術様式を「バロック」といったが、バロックは、ルイ14世の王権が隆盛をきわめる様子を力動的に表現したもので、いわば “男の文化” であった。
▼ ルイ14世

ルイ14世は、対外戦争も数多く指揮し、ナポレオン以前の国家元首として、フランスの最盛期を築いた。
それを象徴するかのように、バロック美術は、グロテスクと思えるくらいのマッチョ感を演出する。

しかし、ルイ14世が活躍したフランス宮廷が落ち着いてくると、フランスの文化様式は、マッチョ感をたっぷり漂わせるバロックから、次第に優美で瀟洒なロココに移行していく。
だから、「バロック」の後に登場してきた「ロココ」の精神には、「もうこの先がない」という、どんづまりの “はかなさ” が漂う。
つまり、「ロココ」とは、フランス革命の動乱を前にした貴族文化の最後の残照だったともいえる。
▼ ロココ的ファッションの女性たち(映画『マリー・アントワネット』 ソフィア・コッポラ監督)

革命の足音が近づいてきても、それを感知する感受性そのものが欠けていた若いアントワネットはいう。
「私は、退屈することが一番恐ろしい」

すべてが過不足なく満たされた人間にとって、「退屈」こそが最大の恐怖なのだ。
18世紀の宮廷社会を生きた貴族たちは、退屈に直面しないためには、朝から晩まで、舞踏会で踊り続けるしかなかった。
しかし、そこには華やかさはあっても、ときめきも高揚もない。
華麗な意匠の裏側には、それを支える何の精神もない。
優美で、洗練されたロココ文化が、同時に退廃と倦怠を秘めているのは、その裏側で、「退屈」という虚無が口を開けていたからだろう。

革命の波に飲み込まれる直前まで、優雅な舞踏をやめなかったフランス貴族社会は、まさに氷山に突き進む豪華客船タイタニック号のようなものだったのかもしれない。
ロココ文化は、その貴族社会の消滅とともに、革命という嵐によって一瞬のうちに吹き飛ばされる。
巨木が切り倒されるようにではなく、シャボン玉の泡のように消える。
その軽さが悲しい。

マリー・アントワネットは、後世に何の業績も残さなかった平凡な王女だったが、ロココの精神を100%体現した人だったがゆえに、その名を永遠に歴史にとどめることになった。
そういう純度100%のナイーブ(アホ)さは、ある意味で、得がたい「気高さ」に通じる。
