CRY ME A RIVER
狭い階段を降りると、素っ気ない木の扉。
扉の上には、古めかしいネオン管のイルミネーション。
『 RUMI 』
この季節、扉の前に立っただけで、その奥から歌声や喧騒が響いてきたというのに、今日はやけに静まり返っている。
… どんな顔をして入ればいいのか。
20年。
いや、それ以上になるか。
ドアを開けると、カウンターの中の痩せた女が、物憂げに首を回した。
「いらっしゃい」
抑揚のない、しゃがれた声が返ってくる。
女の顔を覗き込んでも、乾いた瞳には、何も変化が起こらない。

5人も座れば満席になるカウンター。
2人ほどの人間が隣り合って座れば、もう余裕がなくなるくらいの小さなボックス。
しかし今は、空いた席のどこにも、人影がない。
カウンター脇の壁には、雨に濡れて煙草を吸っている女のモノクロ写真。
ボックス側の壁には、サックスを吹く男の写真。
何一つ変わっていない。
それらの写真が、少し黄ばんで色あせている以外は。


カウンターのストゥールを少し引いて、腰を乗せる。
黙って、女が差し出すおしぼりで、手の甲を拭く。
「バランタインのフィネストを」
「飲み方はどうします?」
「ロックで」
女が、流れるジャズのリズムにアイスピックを合わせながら、軽く氷を割る。
盗み見るように、その腕から首にかけて、視線を這わす。
心もち首の周りの肉がたるんだようだ。
目の下にも、シワが影を落としている。
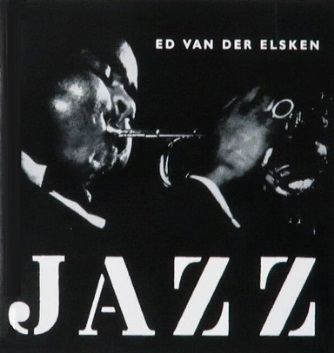
「外、寒いですか?」
女が不意に話しかける。
「外は冷たい雨。夜ふけ過ぎに、雪に変わるかもしれないね」
山下達郎の『クリスマス・イブ』を、ちょっともじってみたが、女は気がつかないか、関心がないようだ。
もっとも、昔から女は、日本の歌などには興味がなかった。
さすがに、20年経つと、人間の顔も変わってしまうものなのだろう。
女の記憶から、私のことは消え去っているようだ。
ならば、はじめての客として振る舞えばいいだけだ。
「クリスマスだというのに、今日は空いているんですね」
「今どきの若い人は、スナックなんかには来ないのよ。スナックで歌うのは老人ばかり。それも、こんな寒い日は、家から出ないわ」
女が差し出すウィスキーを、軽く口に含む。

「こういう店が開いていてよかった。落ち着くよ」
「どういたしまして」
「昔から、こんな店だったの?」
少し間があいて、女の唇が、ふわっと歪むように横に開いた。
笑ったのだろう。
「知っているくせに」
女が、ライターをカチッと鳴らして、煙草に火をつけた。

「やっぱり覚えていたんだね?」
「相変わらず意地悪な人ね。知らんぷりして」
「20年経つのかな」
「22年と3ヵ月」
「詳しいね」
「私が忘れたと思った?」
「思った」
「わけも言わずに、パタッと姿を消して … 。私、朝の駅であなたを探したことが何度もあるのよ。知らないでしょうけれど」
「知らなかった」
「どうせそうよね。… 私も一杯飲んでいい?」
「マッカラムのロックだね」
「そういうことだけ覚えているのね」
22年前。
ふらっと私は、この店に立ち寄ったのだ。
一人きりのクリスマス・イブを持て余して。
誰もいない部屋の灯りを一人で点けて、ベッドに腰を下ろし、孤独な夜にため息をつくのが嫌だったからだ。
だから、わざわざ家から離れた知らない町の駅に降り立って、知らない道を歩き、この狭い階段を降りた。
「今でも歌っているのかい?」
「何を?」
「ジャズ」
「バカね。本気にしてたの?」
「だって、レッスンに行くんだといって、一緒に駅まで歩いた」
「嘘よ」
「どうして、そんな嘘を?」
「あなたがジャズが好きだって言っていたから」
「22年目にして、はじめて明かされた真実か」
「真実を告白する日が来るとは思わなかったわ」
グイとグラスを煽る女の手の甲に、シワが刻まれている。
女は結婚したのだろうか。
薬指に、エンゲージリングのようなものは見えない。
あの手を握ったことがある。
この店に何回目に来たときのことだ。
最後の客が扉の向こうに姿を消し、店の中にたった2人だけ残った夜だった。
照明を少し落とし、フロアでチークを踊った。
確か、流れていた曲が、ジュリー・ロンドンの『クライ・ミー・ア・リバー』。
「もうじき店を閉めて、アメリカで暮らすの」
踊りながら、女は、耳元でそんなことをつぶやいた。
「何のために?」
「何もかも、いやになっちゃったから」
女は、笑ったのか、それともため息をついたのか、お互いに頬を合わせていたから、それは分からなかった。
そのあと、私たちは、どうしたのか。
記憶が途切れている。
したたか酔ったのだろう。

そのようにして店に通うようになってから、何日目だったか。
そうだ。
ラーメンと餃子を食べた。
店にあったワインを持ちだして、そろそろ店じまいするというラーメン屋のオヤジにも振舞って、… それから、明け方まで歩いた。
どんな道を通ったのだろう。
女は猫を飼っていた。
猫は、私を警戒する様子もなく、かといって、歓迎する風でもなく、カーペットの上で彫像のように固まり、無表情に私を見つめた。
その後、女はアメリカに行ったのか、どうか。
こうして、同じ店を維持しているところを見ると、その話も嘘だったのか。
酔いが回ってきているのに、身体が温まらない。
女は同じピッチで飲み続けている。
「寒いね」
「お湯割りに変える?」
「いや、いい。 … 何か歌が聞きたい。ジュリー・ロンドンの『クライ・ミー・ア・リバー』」
「今は、CDもレコードもないわ」
「じゃ、しょうがないな」
「でも、私が歌う。カラオケならあるから」
▼ クライ・ミー・ア・リバー
女の声は物憂く沈んで、部屋の床をすべるように、低く流れた。
昔の記憶が、皮膚の毛穴まで満ちてきて、見えない滴(しずく)となって虚空に散った。
「クライ・ミー・ア・リバー」
… ♪ 川が流れるような勢いで、泣いてちょうだい。
どういう意味なのか?
いまさら、遅いわよ …
そう歌っているようにも思える。
今頃になって、何しに来たの?
そういう歌詞のようにも感じられる。
20年経って、また淋しくなったの?
勝手な人だこと。
もし、淋しいのなら、その証拠を見せてよ。
川のように、ここで泣いて見せたら?
顔を上げて、歌っている女を盗み見る。
突き放したような、笑顔があるだけ。
そこから、女の感情を読み取ることはできない。
灰皿に置かれた女の吸いかけの煙草から、灰がポロリとこぼれ落ちる。
女はそれを横目で見ながら、歌い続ける。

22年前、この女と何があったのか。
もう、それが分からない。