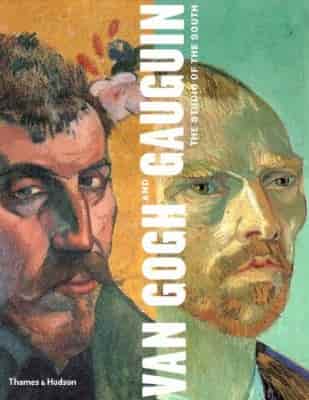
BS放送で『ゴッホとゴーギャン 2人のひまわり』という美術番組を観た。
2時間にわたる長編ドキュメンタリーであったが、退屈することなく、面白く鑑賞できた。
後に「天才」といわれた2人の画家の共同生活
19世紀末。
この時代の西洋美術界を代表するゴッホとゴーギャンという2人の画家は、いっとき意気投合して、南フランスのアルル地方で共同生活を送ったことがあったと、その番組は伝える。
ゴッホ35歳。
ゴーギャン40歳のときだ。

共に暮らしたのは、1888年の10月から12月という短い期間に過ぎなかったが、この共同生活は、どちらの画家にとっても、その後の人生を左右するような大きな意味を持った。

番組によると、共同生活を望んだのは、ゴッホの方だったという。
1887年、ゴッホがモンマルトルのレストランで、ひまわりの絵を展示したところ、その場を訪れたゴーギャンが、ゴッホの絵をいたく気に入り、自分の描いた絵と交換したいと申し込んだとか。
▼ ゴーギャンが気に入ったというゴッホの「ひまわり」(1887年)

そのことに感激したゴッホが、南仏アルルに画家仲間が共同で使えるアパートを借りたとき、ゴーギャンに向かって、「一緒に画業に励もうじゃないか」と声をかけたことが、2人の共同生活の始まりとなった。
ゴーギャンを迎え入れる準備をしていたゴッホは、パリの展示会でゴーギャンが自分の描いた「ひまわり」を気に入ってくれたことを思い出し、さらに別の「ひまわり」の絵を用意して、彼の到着を待った。
▼ ゴーギャンを歓迎する意味で書かれたゴッホの「ひまわり」。同じ構図のものが7点あるとされる

2人の共同生活は、順調にスタートした。
ゴーギャンは、ゴッホが用意した新しい「ひまわり」の絵を気に入り、ゴッホもゴーギャンの絵に尊敬を払い、お互いが刺激し合って素晴らしい生活が続いていくように思われた。
しかし、この2人の芸術家は、あまりにもその個性が違い過ぎたといわれる。
まず、絵画に対する考え方が、真っ向から異なっていた。
ゴーギャンは、目の前にある現実の「風景」や「人物」を絵に仕立てるときも、けっして見た通りには描かない。必ず自分のアイデアを盛り込んで、空想の世界を構築する。
たとえば、下の絵は、ゴーギャンの目指すべき絵画の特徴をよく表しているといわれる『ヤコブと天使の闘い』。
キリスト教の祭りに参加した女性たちが、神に敬虔な祈りを捧げているうちに、彼女たちの前に、奇跡のような光景が訪れる。
それが、聖書の有名なエピソードのひとつ『ヤコブと天使の闘い』である。

画面の右上で、羽根を生やした天使と人間のヤコブが、相撲を取っているのが見える。
つまり、ゴーギャンの絵には、現実にはあり得ない出来事が描かれるのだ。
普通の状態にいる人間の目には映らないが、宗教的法悦に包まれた敬虔な信者には見えてくる「天使」という存在。
要は、想像力が激しく刺激されることによって出現する世界こそ、ゴーギャンが絵画において追及するテーマであった。
要するに、ゴーギャンにとって「絵画」とは、目の前にある現実をそのまま描くのではなくて、「文学」のように、頭の中に浮かんだ世界を描くための手段だったのだ。
それに対して、ゴッホは違った。
ゴッホは、現実に見ている世界をありのままに描くことに喜びを感じるような画家だった。
だから、彼はキャンバスに “ウソ” を盛り込むことができない。
ゴーギャンからすれば、
「その “ウソ” こそ画家の想像力の成果だ」
と主張するところだろうが、ゴッホにとって、画家の空想を画面に盛り込むことは、絵の中に “不純物” を塗り込むようなものだった。
番組では、2人の創作方法の違いを示した実に分かりやすい例を紹介していた。
“ジヌー夫人” というカフェ(酒場)の女主人を描いた絵である。
ゴッホは、アルルに越してきた頃から、このカフェを気に入り、女主人とも親しくしていた。
その女主人をモデルにして、ゴッホとゴーギャンがそれぞれ自分の好きなように肖像画を描いてみようということになったのだ。
視る人ゴッホ、語る人ゴーギャン

▼ ゴーギャン描くジヌー夫人「アルルのカフェにて」(1888年)

見比べてみると、テーマに対する2人の画家の取り組み姿勢の違いが、明瞭に表れている。
ゴッホは、生真面目に “肖像画” という表現にこだわり、背景をばっさり切り捨てて、ジヌー夫人だけをまっすぐ見つめている。
それに対し、ゴーギャンは、「ジヌー夫人がどういう生活をしている人間なのか」ということを、彼女の生活圏であるカフェの様子まで描き込んで説明している。
ゴーギャン描く「ジヌー夫人」の後ろにはビリヤード台があり、さらにその後ろにはテーブルでくつろぐ客たちの姿があり、彼らの吸うタバコの煙すら漂っている。
まるでカフェの喧騒がそのまま伝わってくるような臨場感を盛り込んだゴーギャンの絵だが、実はこの作品は、ゴッホと共同生活を送っている家の中で描かれたものなのだ。
つまり、背後に描きこまれたビリヤード台も客たちも、すべてゴーギャンの脳裏に刻まれた記憶のなかの光景に過ぎない。
それに対して、おそらくゴッホは、ジヌー夫人をカフェにテーブルに座らせ、その場で描きあげたはずである。
背景を描いていないのは、背景を描き込む時間を費やしてまでモデルを拘束したくなかったからだろう。
どちらの描き方が正しいのか、というようなことは問題ではない。
それこそ、それぞれの画家の資質の違いとしか言いようがない。
しかし、どちらが、モデルとなった女性に対して敬意を払っているかということになると、答は明瞭である。
ゴッホが描くジヌー夫人の絵には、相手に対する「尊敬」の念が感じられる。
それに対して、ゴーギャンの方は、モデルの女性を冷ややかに眺めている。
おそらく、ゴーギャンは、このジヌー夫人に対して、ゴッホが感じるような親しみを持つまでに至らず、“ただの酒場女” として意識しただけだったのだろう。
もう一度、2人の描いたジヌー夫人の顔つきを眺めてみよう。
ゴッホの描いたジヌー夫人は、憂いを秘めた表情のまま、視点の定まらない視線を宙に漂わせている。
そこから、彼女の背負っている人間としての苦悩やら孤独感といった内面模様まで伝わってきそうだ。
そして、彼女が尊敬に値する「知性あふれる女性」であることを、ゴッホは彼女の前に書物を並べることで表現しようとしている。
▼ ゴッホ描く「ジヌー夫人」

▼ ゴーギャン描くジヌー夫人「アルルのカフェにて」

それに対し、ゴーギャンのジヌー夫人は、油断ならない目つきをしたまま、店内の客の動向に気を配っている。
ゴーギャンの描いたジヌー夫人からは、酔客たちを上手にあしらす海千山千の女主人というキャラクターが推測されそうだ。
ゴッホがジヌー夫人の前に書籍をあしらい、彼女の知性に対してオマージュを捧げたのに対し、ゴーギャンは酒場の女主人であることを示唆するように、彼女の前に酒瓶 … もしくは水瓶(?)を置いて、彼女の生活環境を説明している。
二つの絵を見比べてみると、ゴッホとゴーギャンの資質の違いがどこにあるのか、それが明瞭に伝わってくるような気がする。
端的にいうと、ゴッホは「人」を見ている。
ゴーギャンは「人」を語っている。
言葉を変えていえば、ゴッホは「絵」を描いている。
ゴーギャンは「文学」を綴っている。
ゴッホは、絵の中に “空想” を盛り込むことは苦手だったかもしれないが、代わりに、モデルの表情や手や指の動きをじっと眺めることで、対象となった人間が抱え込んでいる「生き様」とか「人生」にまで肉薄してしまう。
つまり、ゴッホは「直観」で対象に迫るのだ。
それに対し、ゴーギャンは「言葉」で対象に迫る。
つまり、このジヌー夫人の絵に関していうならば、ゴーギャンは、
「彼女は酒場の女主人であり、自分の店を心地よく演出する技量に長けており、客たちをうまくあしらってお金を稼ぐ能力を持っている」
というように、まず言葉で状況を分析し、それをそのまま絵に “翻訳” している。
ゴーギャンが描いた「狂ったゴッホ」
同じ画家同士といいながらも、このようにまったく異なる芸術観を持った2人の共同生活は、すぐさま激しい緊張をはらむことになった。
ゴーギャンは、ゴッホに対し、
「もっと絵のなかに自分の想像を盛りこめ」
と説く。
「絵画というものは、目に見えないものを可視化させる芸術なのだから」
という彼の持論を、ゴッホに強要する。
ゴーギャンのいう「想像」とは、すなわち「観念」のことである。
「思想」といってもいいし、「哲学」といってもいい。
いずれにせよ、言葉で紡ぎ出した想念に、キャンバスの上で可視的な「形」を与えることが、ゴーギャンにとっての「想像」なのだ。
一方のゴッホは、そんなことよりも、ゴーギャンの色使いや絵の具に塗り方が気に食わない。
「自然の陽光をたっぷり受けた景色ならば、もっと明るい黄色が強調されなければならないはずなのに、なぜ陽の光を帯びた風景がくすんだ橙色になってしまうのか?」
ゴッホにとっては、絵の中に画家の想像を盛り込むことなどよりも、そんな想像にとらわれて、現実の光を見ないゴーギャンの方が、絵の本筋から外れているという思いがある。
2人の間に議論が生まれると、それはどんどんヒートアップしていき、やがては、お互いの神経がズタズタになるまで繰り広げられるようになった。
この頃、ゴーギャンがゴッホのことをどう思っていたかということが如実に伝える1枚の絵がある。
『ひまわりを描くゴッホ』という絵だ。

アトリエの床にイーゼルを立てかけ、ひまわりを眺めながら、ゴッホがそれを描きこんでいる。
若干、さびしそうな表情を湛えているゴッホ。
しかし、それ以外には、この絵から2人の間に特別な確執があった兆候は読み取れない。
だが、芸術心理学のようなものを研究している学者から見ると、この絵にはゴーギャンがゴッホに対して抱いていた感情が “露骨なまでに” 滲み出ているという。
まず、ゴッホを描くゴーギャンの視点。
「上から目線」である。
つまり、ゴーギャンはゴッホを見下ろすことによって、暗に自分の優位性を確認しているということになる。
そして、この絵の方に描かれている橙色と茶褐色の帯のような模様。

この “模様” のように見える帯状のものは、当時ゴーギャンがこのアトリエで描いていた自分の絵の一部なのだそうだ。
そのことからも、ゴーギャンが、ゴッホの描いてる絵より、自分の描いている絵の方が上側に位置していると思っていた節がうかがえる。
そして、ゴーギャンの絵とゴッホの絵を間を埋めている “水色の床” 。
色彩心理学では、青系の色というのは、「距離」とか「へだたり」を意味する色だとか。
そう考えると、ゴーギャンは、自分の作品とゴッホの作品の間には、そうとうな “距離” があると感じていたことが伝わってくる。ゴーギャンからすれば、それこそ、「自分とゴッホの才能の差である」と思っていた可能性すら否定できない。
しかし、そういう学者たちの心理学的なアプローチが、実際には、どれだけゴーギャンの気持ちに迫っていたかどうかは、分からない。
番組では、そのような解釈がまことしやかに語られていたが、もちろん推論の域を出ない。
ただ、この絵のモデルとなったゴッホは、ゴーギャンの絵に対していい気分を持っていなかったことだけは確かなようだ。
絵の感想をゴーギャンに求められたゴッホは、次のように語ったという。
「ここに描かれているのは確かに僕だ。しかし、これは気が狂ったときの僕の姿だ」
実際、ゴーギャンとの精神的な葛藤に疲れたゴッホの精神には、徐々に破綻の兆候が表れていた。
自分の耳を切り落とす
この頃のゴッホの心境はどのようなものであったのか。
尊敬していたゴーギャンに自分の創作技法を否定され、自信を失いかけていたゴッホは、アブサンというアルコール度数の高い酒を浴びるように飲んで酩酊する日が多くなったという。
酔ったゴッホは、酒を飲んでいたグラスを突然ゴーギャンに向かって投げつけたり、カミソリを抱えたまま、ゴーギャンの後を付けたりするという不可解な行動を取るようになったとも伝えられている。
そして最後は、そのゴーギャンに突き出したカミソリを自分に向け、自分の耳を切り落として、娼婦のもとに差し出すという、あの有名な “耳切り” 事件が起こる。
その話を知ったゴーギャンは、共同生活の終焉が訪れたことを意識したはずである。
▼ 耳を切り落とした後のゴッホの自画像

ゴッホの行動が、ゴーギャンへの「怒り」や「失望」からきたものか、それとも自分から離れようとしているゴーギャンに対する「愛着」の不器用な表現だったのか、ゴッホの内面を推測するのは難しい。
ただ、ゴッホがこの頃から精神疾患を患っていたと推測する研究家は多い。
精神疾患の症状に関しては、てんかん説、統合失調症説、アブサン中毒説などいろいろ考えられるらしいが、定説はない。
そのような病気の影響も多少あったにせよ、性格的に、もともとゴッホが並外れて感情の “濃い” 人間であったことは確かだ。
こういう人間と共同生活する人は、おそらくどんな寛容な人格を持っていたとしても、いつしか疲労困憊してしまうだろう。
1888年の12月。共同生活に疲れたゴーギャンは、ゴッホのもとを去る。
凄絶な生き方を示したゴッホ最後の作品
ゴーギャンと別れた後のゴッホは、どうしたのか。
耳切り事件を起こした後、しばらくアルルの病院で治療を受けていたゴッホは、翌1889年の1月に退院。
5月にはアルルを去り、サン・レミの精神病院に移る。
この頃、ゴッホは、
「自分は毒を盛られている、至る所に囚人や毒を盛られた人が目につく」
などと訴えていたというから、耳の傷は癒えても、精神疾患の方はけっして快方に向かったわけではなかったようだ。
しかし、アルルを離れてからのゴッホの制作活動はますます旺盛になり、後に “傑作” といわれる作品群が次々と誕生することになる。
一連の作品のなかでも、ひときわ精彩を放っているのが、病院の鉄格子越しに見た夜景を描いたといわれる『星月夜』だ。
▼ ゴッホ「星月夜」(1889年)

きらめく星々と、太陽のように輝く月。
そして、水底から浮上していく深海魚のような糸杉。
何よりも目を引くのは、画面中央でのたうちまわる雲だ。
うねる画面の中を、いっときも休むことなく動き続ける星、月、雲、糸杉。
すべてが、霊魂のような妖しげな光を帯び、この世のものとは思えない不思議な生命力をみなぎらせている。
ゴッホは、この絵に関して、
「実物そっくりに見せかける正確さではなく、もっと自由で自発的デッサンによって、田舎の自然の純粋な姿を表出しようと思った」
と述べているという。
ゴーギャンと別れることによって、精神の危機まで迎えながら、ようやくゴッホは、ゴーギャンの言っていた「実物そっくりの自然ではなく、心に浮かんだ自然」を描きあげたということになる。
だが、ゴッホの「心に浮かんだ自然」というのは、「自然」という形を取った自分の「心」だった。
妖しげな光を帯び、この世ならぬ生命力をみなぎらせている「自然」。
それはそのまま、溶鉱炉のような炎を燃え盛らせながらも、不安定に揺らぎ続けるゴッホ自身の「心」だといっていい。
下は、ゴッホの最晩年の作といわれる『カラスのいる麦畑』。
▼ ゴッホ「カラスのいる麦畑」(1890年)

この絵を描いた後に、ゴッホは「自殺」ともいわれる謎の死を遂げる。
通説では、戸外で写生中に、発作的に銃で自分の胸を射抜いたといわれているが、その動機や銃を撃った場所などは特定できていない。
しかし、もし自殺だとしたら、上の絵がその遺書のようなものに当たるのかもしれない。
そう思って、あらためて麦畑の絵を視てみる。
すさまじい荒涼感が伝わってくる。
麦畑の麦は、押し寄せる津波のように沸き立ち、空を見上げると、昼間なのに、至るところから夜の闇が滲み出てきている。
画家の視線は、まるで、この世の終わりの風景を凝視しているかのようだ。
その終末の気配をあおるかのような、カラスたちの不吉な影。
カラスは、この世と冥界をつなぐ使者の鳥といわれている。
ゴッホは、おそらくこの絵が “遺書” になることを予感していたのだろう。
飛び立つカラスの群れは、そのまま自分の魂を冥界へ連れる使者たちの姿に思えたはずだ。
そう眺めてみると、この絵から漂ってくる深い寂寥感の秘密も解けそうに思えてくる。
しかし、この絵のはらんでいる力強さは、いったいどこから来るのだろうか?
それは、精神の危機に見舞われながらも、自分の精神が破たんしていく最後の姿を見届けようとする画家としてのすさまじい好奇心のせいではなかろうか?
「この世が終わるのなら、どのように終わるのか、しっかりこの目で見届けてみたい」
その探究心の激しさが、この絵から伝わってくる。
そういった意味で、彼は最後の最後まで、まるで肉食獣がエサに襲い掛かるように、描くべき対象に激しく肉薄していく画家であった。
ゴーギャンの旅立ち
ゴッホが37歳で息を引き取った1890年の夏。
ゴーギャンは、太平洋に浮かぶフランス領タヒチ島へ渡るための最後の準備をしていた。
タヒチは、ゴーギャンにとって、“原始の精神に満ちた未開の聖地” であり、“ヨーロッパ近代文明に毒されない最後の楽園” であった。
ゴーギャンは、その地で自分のテーマを見つけ、ヨーロッパ画壇に新風を吹き込むことを夢見ていた。
渡航準備中に、ゴッホの弟である画商のテオから、ゴッホの訃報が届く。
ゴーギャンは、すぐさま追悼の手紙を書いた。
文面には、
「ゴッホは自分たちの時代における数少ない本当の芸術家であり、死後その作品のなかに彼は生き続けることだろう」
と書かれていたという。
そして、手紙の文末には、
「自分は今後この目と心で、ゴッホの作品を通して彼に会うつもりである」
という結びの言葉が添えられていた。
絵画論においては対立があったが、ゴーギャンはゴーギャンなりに、やはりゴッホの天才性を見抜き、それが自分の画業にも影響を及ぼすだろう、と予感したのかもしれない。
ゴッホの後を追って
実際、タヒチで暮らすようになってからのゴーギャンの絵は、アルル時代のゴッホが描いていたように、南国の陽光をふんだんに採り入れた明るいものに変わっていった。

ゴーギャンは、タヒチでようやく自分のテーマを見つけたともいえる。
実際に、ゴーギャンの代表作といわれるものの多くは、このタヒチ時代に生まれている。
▼ ゴーギャン「アレアアレア」(1892年)

しかし、やはりゴッホの画風とは明瞭に異なる部分がある。
たとえば、タヒチ女性を描いた下の絵などに漂うアンニュイ(物憂い雰囲気)は、いったいどこから生まれて来るのだろう。

「原始の生命力に溢れ、人間の根源的な歓喜をそのまま温存した南太平洋に浮かぶパラダイス」。
それを求めてタヒチに来たはずなのに、ゴーギャンの筆使いによって描き出される女たちは、時間の止まった世界を生きるような、どこか物憂い疲労感に包まれている。
ゴッホも、社会の底辺に生きる疲れた人々をたくさん描いてきたが、このような人間のアンニュイを一度も描いていない。
ゴーギャンの筆からしたたり落ちるアンニュイは、実は、彼が求めてきた「原始の輝き」が、実態の伴わない観念でしかなかったところに由来する。
一説によると、彼が訪れた19世紀末のタヒチは、フランスの植民地として、そうとうな文明化が進んでおり、固有の宗教も衰退してキリスト教化されていたという。
そこで流通する商品も、ヨーロッパ製の工業製品が大半を占めるようになり、ゴーギャンの描くタヒチ女性たちが身にまとっている衣装ですら、ヨーロッパからの輸入生地で作られていたといわれている。
その事実を見つめながら、あえてゴーギャンは “文明に毒されない原始の楽園” を描き続けた。
しかし、そのような噛み合わない意識の隙間から、あの “時間が止まったような物憂さ” が滲み出てきたのではあるまいか?
ゴーギャンにそのような制作姿勢を可能にさせたのも、もともと彼が、目から入る情報よりも、自分の脳裏に浮かぶ観念に頼って絵を描く画家だったからである。
その代表的な例が、1897年に描かれた『われわれはどこから来たのか。われわれは何者か。われわれはどこへ行くのか』という絵であったかもしれない。
▼ ゴーギャン「われわれはどこから来たのか。われわれは何者か。われわれはどこへ行くのか」(1897年)

ゴーギャンが作り出した答のない永遠の問
「われわれはどこから来たのか。われわれは何者か。われわれはどこへ行くのか」
横幅4m近くになろうとするこの大作では、画面の右から左にかけて、人間が誕生し、死に至るまでのプロセスが、タヒチの風俗を借りて描かれているという。
しかし、もとよりこの絵の中に、タイトルのはらんでいる「問」に対する「答」があるわけではない。
こういう問に対して、答などない。
哲学者も宗教家も答えきれない。
だから、この問はいつまでも、“永遠の問” として生き続ける。
私はこの「問」こそ、人間が抱えてしまった「問」のなかでも、もっとも美しい「問」であるように思うのだが、しかし、そもそも「絵画」にこういうタイトルを付けてしまう才能というのは、画家の才能ではない。
それは詩人の才能である。
ゴーギャンはゴッホとは違って、最後まで “文章を書く” ように絵を描いた画家であった。
20世紀に入った1903年。ゴーギャンはタヒチの地でこの世を去る。
ゴッホと同じく、死因ははっきりしない。
もともと、死の2年前ぐらいから、ゴーギャンの体力は落ち込んでおり、体の痛みも激しかったという。
死因は、その痛みをやわらげるために頼っていたモルヒネの多用による心臓発作ではなかったかと推測されている。
ゴーギャンの体から、次第に気力と体力が奪われ始めた頃、彼は故郷フランスの知り合いに頼んで、ひまわりの種を送ってもらっている。
タヒチには南国の植物が群生していたが、北アメリカを原産地として広くスペイン、フランスに普及したひまわりだけはなかったのだ。
届いた種でひまわりを栽培したゴーギャンは、やがてその花を肘掛椅子の上に置き、ひとつの絵を仕上げる。
▼ ゴーギャン「肘掛椅子のひまわり」(1901年)

ひまわりへの回帰
ひまわりこそ、ゴッホとゴーギャンを結びつけた花だった。
それは、かつてアルルで共同生活をしたとき、ゴーギャンもゴッホもさんざん見てきた花であり、フランスでは少しも珍しい花ではなかった。
ということは、想像力で絵を描くゴーギャンならば、記憶のなかの「ひまわり」を基(もと)に絵を仕上げることなど造作もないことだったろう。
しかし、最晩年になってようやくゴーギャンは、ゴッホのように現物のひまわりを見ながら絵を描く気になった。
実際に描かれたゴーギャンのひまわりは、タヒチで描かれた一連の絵とはやはり一線を画する。
アルルの匂いがするのだ。
ゴッホとともに暮らした、南フランスのアルルの太陽が感じられる。
死期が近づいてきたゴーギャンが、“ゴッホの花” であった「ひまわり」を描こうと思ったのは、果たしてどういう心境からだったのだろう。
ゴッホへの友情からだろうか。
それとも、永遠のライバルであったゴッホへの対抗心からか。
いずれにせよ、ゴーギャンが終生、ゴッホという一人の男を忘れずに生きてきたことだけは確かである。
「自分はゴッホに勝ったのか、負けたのか」
その答は、最後までゴーギャンにも分からなかったに違いない。