「推理小説」といわれるものを、ほとんど読んだことがない。
好き嫌いというレベルではなく、トリックとか “からくり” といったたぐいのものが、能力的に理解できないのだ。
つまり、そういう理数的な “構造体” を理解する力が自分には致命的に欠けていて、小説を読むというより、苦手だった物理学の教科書でも読んでいるような気分になってしまうのだ。
いっぽう、うちのカミさんは推理小説が好きである。
だから、それを読まない私をバカにする。
そのため、
「あの手の読み物は、小説なんかじゃなく、パズルだよ」
… と、私は負け惜しみをいったりするのだが、いつもカミさんに冷笑されるだけで終わる。
そんな自分が、どういう風の吹き回しか、松本清張の『点と線』を読むことになった。
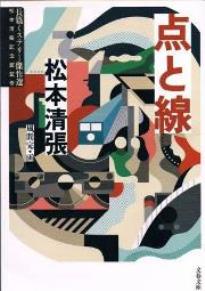
理由は、ただの “気まぐれ” 。
本屋の店頭で、たまたま引き抜いたこの文庫本(文春文庫)をペラペラめくっているうちに、挿し絵が挿入されているのに気づいたからだ。
もちろん、この作品が日本の推理小説の古典的名作であることは知っている。
テレビでも、いろいろなキャストによって何度かドラマ化されて、それぞれ評判をとっている。
しかし、今回この本を読む動機になったのは、この挿絵の力が大きい。

挿し絵画家の名は風間完。
その絵が、本の活字と活字の間から、寂しげな昭和中頃の風景を浮かびあがらせている。
どちらかというと、暗い絵である。
そして、その暗さの底に、今はこの世から消えた “幻の昭和” の貧しさと寂しさが潜んでいる。

結局、“絵” に惹かれて、その文庫本を買った。
買ったからには、読まなくてはならない。
読んでみると、これがなかなか面白い。
松本清張は、歴史モノはよく読んだが、推理小説は、前述したような事情で、まるっきり読んだことがなかった。
しかし、日本を代表する推理小説家の文章だけあって、まず情景描写がツブ立っている。
事件の発端となった博多湾を見下ろす香椎灘(かしいなだ)の荒涼とした風景。そこに至るまでの、寂れた町の空気感。
この作家は、そういう描写が芸術的にうまい。
文章から、海の匂い、風の冷たさがびゅんびゅん肌を刺してきて、登場人物といっしょに自分がその場を歩いているような気分になる。
登場人物たちの会話も手馴れたものだ。
まるで、芸達者な役者たちの演じるドラマを見ているような味わいがある。
推理小説はみなパズルのようなものと思い込んでいたが、やはり一流の作品になると、しっかり “文学の香り” を持っているものだと思った。
しかし、肝心の謎解きの部分に来ると、もう解らない。
この小説では、東京駅にたった4分間だけ、はるか遠くに離れたホームに止まっている列車が丸見えになる時間帯があり、それを巧妙に利用した(あの、あまりにも有名な!)トリックが仕組まれているのだが、それがどうして「トリック」になるのか、その構造がもう頭に入って来ない。
ましてや、主人公の刑事が、複雑な列車時刻表のからくりを一つ一つ読み解いていくあたりになると、もう飛ばし読み。
それでも、なんとかストーリー展開についていけたのは、人間の “格闘” にリアリティがあったからだ。
刑事たちが、犯人を追いつめるときの執念といおうか、情熱といおうか、その熱い心の鼓動だけは生々しく伝わってくる。
ここに登場する犯人は、ものすごく頭がいい。
しかも理数的な頭脳の持ち主なのだ。
複雑な列車時刻表を、それこそパズルを楽しむように縦横無尽に駆使して、鉄壁のアリバイ工作を施す。

それに翻弄される刑事たち。
しかし、頭脳の緻密さにおいては犯人に及ばないものの、情熱のほとばしりにおいては、刑事たちの方が犯人に勝る。
そこのところだけは、理数系の訓練をまったくサボってきた自分にも、かろうじて理解できた。
そして、そういう情熱のドラマは、永遠不滅だ。
この小説を成立させた環境は、もう歴史のかなたに遠ざかろうとしている。
新幹線があり、飛行機の利用が当たり前になり、携帯電話が普及した現代社会では、もうこのようなトリックを仕組んだ小説が生まれる余地がない。
なのに、古びていない。
というよりも、逆に、失われた世界をさまようような奇妙な目新しさが漂ってくる。
昔の鉄道の、ローカル線の窓の外に広がる情景。
その硬い椅子の座り心地。
ホームや待合室の風景。
それが、ノスタルジックであり、かつ新鮮だ。

もしかしたら、鉄道ファンの人にとっては、とてつもなく興味をそそられる読み物ではないかという気がするのだが、私はそれほど鉄道趣味があるわけでもないので、そこのところはよく分からない。
ただ、犯人のアリバイ崩しのプロセスが、鉄道の旅と重なっていることだけは確かだ。
この小説に、最後まで甘酸っぱい叙情が漂っているのは、たぶん「旅」がサブテーマになっているからかもしれない。「旅情」があるのだ。
最後のドンデン返しには、ハッとする。
凄惨な殺人描写も、スリリングな追跡劇もない小説ながら、一番最後に「人間の怖さ」というものが余すところなく活写されていて、鬼気迫るものがある。
それも列車の時刻表という、数字ばかりの無味乾燥な実用データが、逆に人間の奇怪な情念を暴き出すという設定だから、なおのこと怖い。

やはり、この作品は、「人間」を描いた小説だからこそ、古典としての生命を獲得したのだろう。
「真犯人が特定されてしまえば謎解きが完了するため、推理小説は再読に耐えない」
と、よく言われる。
しかし、それはテレビの2時間ドラマのようなサスペンス劇にはいえることかもしれないが、「人間」をテーマに据えた文芸的な推理小説には当てはまらない。
この最後の衝撃をもう一度味わうために、いつの日にか、自分はこの作品を(犯人が分かっているにもかかわらず)再読することになるだろう。