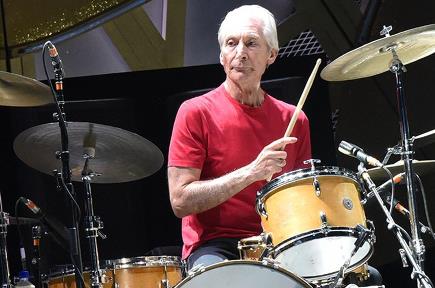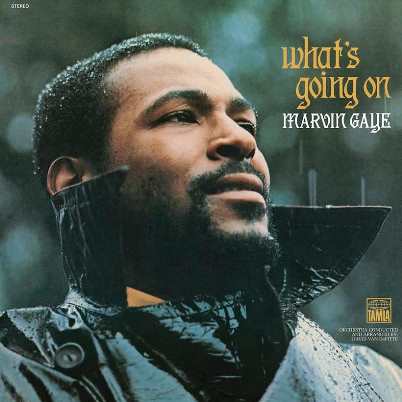毎年、8月も中旬になると、マスコミなどでは、「終戦の日」(8月15日)にまつわる報道特集が多くなる。
私が毎週見ている『関口宏のもう一度! 近現代史』(BS-TBS土曜日)においても、ちょうど日本が太平洋戦争に負けていく過程が克明にレポートされている。

その番組をじっくり見ていると、あの戦争の末期はほんとうに悲惨だったということが分かる。
沖縄戦では、日本兵と同時に多くの民間人が戦争のために命を失い、東京では、連日のようにアメリカ軍のB29による爆撃によって、市民が殺戮されていった。
そして、その ”トドメ” が、広島と長崎に対する原爆投下だった。
そういう76年前の状況を見ていると、「なんか似ている!」と思わざるを得ない。
コロナ禍を、仮に “戦争” に見立てると、沖縄のコロナ感染者の数は8月12日には過去最多(約700人)を記録し、人口10万人あたりの罹患率では日本では最悪という数値を示した。
さらに、13日における東京の感染者数は5,773人。過去最多の記録だという。
まさに、原爆投下を迎えていないところだけが違うといえるが、今の日本の沖縄と東京に集中するコロナウイルスの惨事は、太平洋戦争末期に迎えた状況と似ている。
あの太平洋戦争の終盤、日本政府はすでになすすべを失っていた。
1944年(昭和19年)、首相・陸軍大臣・内務大臣を兼ねて絶大な権力を握っていた東條英機は、サイパン陥落の責任を取る形でその内閣を総辞職した。
しかし、首相を辞めた東條を含め、当時の日本政府は連合国と講和をするでもなく、「日本人全員の本土決戦」という悲惨な標語を連発するだけで、ジリ貧になっていく日本の状況を直視せず、いたずらに時間を費やした。
その間、戦場となった沖縄と空襲にさらされた東京では、軍人・民間人の別なく、多くの日本人の生命が失われていったことは、歴史が伝えるとおりである。
戦後、多くの識者が書いた評伝によると、
「東條英機という軍人は、首相になるまでは有能な実務官僚であったが、首相になってからは、情緒的な精神論ばかり振りかざし、日本が置かれた難局を理解する能力に欠けていた」
という。

なんだか、似たような人が現在もいることを思い出す。
「官房長官時代は、辣腕(らつわん)を奮う有能な政治家であったが、首相になったとたん、国民へのメッセージ力が希薄な答弁しかできないリーダーでしかないことを暴露してしまった」
… と思えるような政治家が。
言わずと知れた菅義偉(すが・よしひで)首相である。

東條英機と菅義偉氏に共通した性格的特徴をいえば、まず真面目。
実務家としてはそうとう有能。
ただし、政治家としての大局観に乏しい。
権力欲はあるが、“独裁者” に徹するほどの能力はない。
つまり、カリスマ性がない。
ユーモアのセンスもない。
そのため、国民に対して、同じ標語を繰り返し発信するしか能がない。
戦争末期、東條英機は、ひたすら「聖戦完遂・本土決戦」を叫んで、情緒的に国民を煽っただけだった。
そこでなされた主張は、論理も科学性もないもので、ひたすら彼の主観的な願望が吐露されたものにすぎなかった。
彼は、とにかく「負けることを恥」とした。
だから、大都市への米軍の空襲が激しくなり、学童疎開が議論され始めたときにも、東條英機だけは「学童疎開」に反対したという。
「疎開などすると、この戦いは負け戦だと日本国民がみな思い始めるからだ」
とか。
また、
「戦いで負けたら、敵に捕虜となることを恥じて、自決しろ」
という “戦陣訓(せんじんくん)” の思想を徹底させたのも東條である。
そのため、多くの日本兵は捕虜となって救われる道を自ら閉ざし、米軍の前で自決する道を選んだ。
とにかく彼は、国民を合理的・科学的に説得する術を持たず、ただただ一つの命令を繰り返すだけの人だった。
現在の菅首相はどうか。
コロナ禍において、彼が唯一言い続けていた言葉は、「国民の安全・安心を守る」という標語だけで、それを説明する内容はまったくない。
「オリンピック開催」にのめり込んでいた時期においても、
「人流の抑制に注意を払いつつ安全・安心を確保した大会を心がける」
という言葉を繰り返すだけだった。
これは、ある意味、“失語症” を吐露したようなものである。
つまり、国民が納得できるメッセージを発することができなかったのだ。
太平洋戦争の話はさておき、現在の菅義偉氏が抱えている問題は、今回の「東京オリンピック2020」を側面から浮き彫りにしているようにも思える。
今回のオリンピックで、日本発の情報として世界に訴えかけるものは何だったのだろう?
コンセプトは「多様性と調和」だというが、大会を通じて、それがどのように表現されたのかは、はっきりしたものが見えない。
少なくとも菅氏のメッセージからは何も読み取れない。
確かに、“多様性” を志向した新しい提案はなされた大会だった。
LGBTの問題、人種差別への抗議の問題、それを浮き彫りにしたアスリートもたくさん輩出した。
しかし、そういう問題に対して、菅首相自身がどのようにコミットしたのかは、本人の行動から何も見えてこない。
菅氏がオリンピックを開きたかった最大の理由は何だったのだろう?

もちろん、一番の理由は、五輪開催がもたらす経済効果と、それによって世界の日本に対する称賛が高まることだった。
しかし、それを国民に説明する言葉は、非常に情緒的なものだった。
1964年の第一回東京オリンピックを、菅氏は高校時代に体験した。
そして、
「東洋の魔女(日本女性バレーボールチーム)の美技に目を見張り、日本柔道の行く手を遮ったヘーシンク(オランダの柔道家)の驚異に触れ、スポーツの魅力にとりこになった」
という。
そして、彼は、
「今の若者と子供たちに、夢と感動の機会を与えたかった」と付け加えた。
私もまた、中学生のときに、64年の東京オリンピックをリアルタイムで経験している。
だから、世代的に、彼の無邪気な感動も分かる気がするが、一方で、そんな昔のことを掘り返してどういう意味があるのか? … という白けた気持ちも込み上げてきた。
「スポーツの力」、「夢と感動」。
私の個人的な感覚を吐露すれば、一国の首相が、こんな無邪気な言葉でオリンピックを語ってしまっていいものか? … という思いがある。
ナイーブすぎる。
それが仮に本音だとしても、すべての国民が菅氏の感覚に共感できるとは思えない。
スポーツを経験したことのない菅氏の観念的な言葉と、実際繰り広げられた世界のアスリートたちの死闘とは、あまりにも隔たりが大きすぎる。
感動できるのは、あくまでもアスリートたちの美技であり、菅氏の言葉ではない。
「無邪気さ」は、時には罪である。
私は、菅首相の無邪気さは、五輪ソフトボール日本代表の後藤希友投手の金メダルをいきなり噛んだ河村たかし名古屋市長の鈍感さと通じるものがあるように感じる。

菅首相の年齢は72歳。
河村市長も72歳。
(意味はほとんどないが、二人とも血液型はO型だ)
ともに「団塊世代」(1947年~1949年)のまっただなか。
企業人としては、すでにこの世代はみなリタイヤしている。
しかし、政治家としては、この世代の人間はみなしぶとく生き残っている。
私(1950年生まれ)も、この世代の末席に位置する人間であるから、彼らの心情は良く分かる。
この世代は、10歳頃に、東京タワーが着工された映像を記憶にとどめている。
多少の余裕ある家には、スバル360が納車され、その支払いを、できたばかりの1万円札で払った。
そして、子供たちは、坂本九の歌う『幸せなら手をたたこう』の明るい歌詞を口ずさみながら学校に通った。
やがて、ファッションとナンパを柱とした雑誌『平凡パンチ』(1964年発行)を読みふけって “若者文化” を知り、東京~大阪間を3時間で移動する新幹線の存在を知った。
菅氏も河村氏も、そういう “新時代” の到来を目の当たりにしたときに、最初の東京オリンピックを迎えた。
だから、彼らのオリンピック観は、若い頃に味わった「膨張感」「高揚感」と切り離すことができない。
基本的に、団塊世代の人々は、(おそらく死ぬまで)、自分が少年時代に体感した右肩上がりの高揚感を捨て去ることはできないように思える。
そういう精神構造が、菅氏と河村氏の心を支配している。
それは、「すべて自分中心に世界を見てしまうクセ」だ。
菅首相は、五輪が終わったあとのインタビュー(8月11日付の米誌「ニューズウィーク」)において、
「開会前には問題もあったが、五輪が始まってからは、選手たちの見せる活躍で、多くの日本人が、スポーツの力に感動し、元気づけられた」
と述べた。
この感想は、ある一面を言い当てているかもしれないが、そこに彼の客観的な裏付けはない。
すべて彼個人の主観的願望が表出しただけだ。
一方の河村たかし市長。
彼は、五輪ソフトボール代表の後藤希友投手の金メダルを噛みながら、「早くええ旦那をもらって結婚しなさいよ」とか言ったらしい。
昨今は、この表現自体が “セクハラ” に認定される時代であるが、河村氏は悪びれることなく、
「自分は若い人に対しては、必ず “彼女はおるのか?” 彼氏はいるの? ” 」と聞いているという。
理由は、「そう聞かれると若い人はみな喜んで、気持ちをリラックスさせるからだ」とか。
この恐ろしいほどの社会とのズレ!
すでに、この世代は、社会に向けて発言できる場を国民や市民と共有できていない。
そういうことが浮き彫りになってしまった今回の五輪騒動だった。