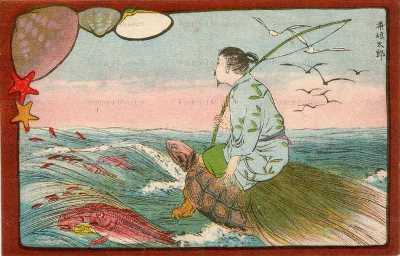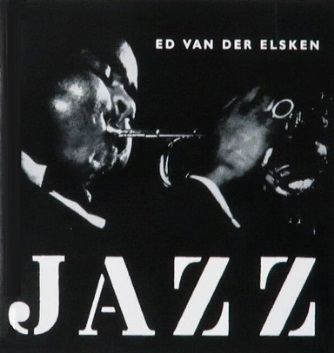萱野稔人(かやの・としひと)著
『リベラリズムの終わり その限界と未来』
(2019年11月20日 幻冬舎新書)の感想

惜しい本である。
「狙い」はいいと思った。
しかし、結論を急ぎ過ぎたのか、なんとも消化不良を起こしたまま
発行されてしまった本という気がする。
最大の問題は、『リベラリズムの終わり その限界と未来』というタイトルを掲げながら、肝心の “リベラリズム” の定義をあいまいにしたまま議論が進んでしまったことだ。
さらにいえば、「その限界と未来」という副題を持ちながら、(“限界” の方は多少説明されているけれど … )“未来” の方にはほとんど言及がないことも中途半端だ。
確かに、ここ数年、「リベラル派」もしくは「リベラルな運動」というものに対し、世界中で批判が起こっていた。
そして、それに呼応した書籍も出回るようになり、ネット言論でも「反リベラル」を謳う主張が目立つようになってきた。
萱野氏は、それらを見据えて、
「今さらリベラルの定義は必要ないだろう」
と、はしょっちゃったのかもしれない。
そうだとしたら、ますますもって残念な本である。
世の風潮が「反リベラル」に向かっていたとしても、萱野氏なら、その理由について、独特の社会分析を踏まえ、さらに、哲学と思想の領域から読者に納得のいく解説をしてくれるのではないかと期待したからである。

実は、私はこの萱野稔人(写真上)という哲学者をわりと高く評価していた。
彼が世に広く知られるようになったのは、10年ほど前に放映されていたNHKの討論番組『ニッポンのジレンマ』で、切れ味の鋭い社会批評を提示してからである。
その後、彼は、専門分野の哲学のみならず、経済、政治、歴史と幅広い学問領域を横断的に渡り歩き、数々の研究成果を残してきた。
特に、経済学者の水野和夫氏との対談による『超マクロ展望 世界経済の真実』(2010年11月)という本では、資本主義の勃興からグローバル経済の先行きまで見通す視野の広い分析を行い、当時これを読んだ私はすごく興奮した記憶がある。

だから、当然この『リベラリズムの終わり』という本も期待して手に取った。
しかし、残念なことに(冒頭に記したように)、この本では「リベラル」という概念をしっかり提示することもせず、いきなり、
「ここのところ『リベラル』といわれる人たちへの風当たりがひじょうに強くなっている」(序章)
と一気にたたみ込んでいく。
そういう展開に持ち込むのなら、少なくとも、“リベラル” といわれる人たち … って何? という読者の素朴な疑問に、まず最初に答えるべきではなかったろうか。
現在マスコミで、「リベラルな人たち」といえば、それは「保守的な人たち」に対して、「革新を標榜する人たち」というイメージで語られることが多い。
政党でいえば、「政権与党」の自民党に意見をいったり批判したりする野党の「立憲民主党」や「共産党」のことを指す。

また、テレビの『朝まで討論会』などでは、自民党的見解を述べる人たちに対し、激しく非難する学者や評論家のことをいう。
基本的には、「反原発」、「反米軍基地」、「反戦」、「反憲法改正」などと “反” を最初に掲げて思想を語る人たちといってもいいのかもしれない。

しかし、そういう人たちを「リベラル派」とひとくくりにまとめてしまうのはどうなのだろう?
そもそも「リベラル派」とは、何なのか?
それは、かつて「左翼」と呼ばれていた人たちが、そのまま「リベラル」と呼ばれるグループにスライドしたものなのか?
それとも、旧「左翼」とは異なる新しい思想をもった人々なのか。
「リベラル」の直訳語が「自由」なら、その言葉をまっ先に掲げ、かつ「民主」という言葉と組み合わせた「自由民主党」などは “最大のリベラル党” ということにならないのか?
どうもそこのところがよく分からない。
そこを萱野氏に教えてほしいと思ったのだが、しかし、氏は、そういう概念区分を言及することを避け、一気に、「リベラルが嫌われる理由」の説明に移っていく。
すなわち、リベラルな人々が嫌われるのは、
「口ではリベラルなことを主張しながら、実際の行動はまったくリベラルではない人がたくさんいる」からだ、という。
つまり、萱野氏の回りには、リベラル派を自認しながらも、「学生や大学職員、若手研究者に対してきわめて権力的にふるまう人も少なくない」とか。
そして、次のように続ける。
「欧米諸国でも日本でも、リベラル派の主張は現在、かつてほどの支持を集められなくなっている。
それは、リベラル派の人間が、自分たちのご都合主義に無自覚なまま独善的に “正義” を掲げるという “にぶさ” に、多くの人がうんざりしているからである」
こんなくだりも。
「リベラル派の人間は、自分たちの主張に支持が集まりにくくなっている現状を、“人々の意識の低下” や “社会そのものの劣化” だと批判する。
そして、批判者に対してしばしば “反知性主義” というレッテルを貼る。
しかし、そのレッテルは、むしろリベラル派にこそふさわしい」(第一章 76ページ)
さらに、彼は、上記のことを言葉を変えて繰り返す。
「リベラル派は、自分たちの言動が批判されるようになったのは、人々が右傾化したからだ、という。
しかし、本当にそうだろうか。
そもそも “右傾化のせいだ” という主張そのものが、『リベラル派こそが正しく、それを批判する人間はおかしい』という前提に立った認識だ。
そこに、彼らの “にぶさ” があらわれている」
まぁ、こういうように「リベラル批判」がとめどなく噴出してくるので、「反リベラル」の立場を標榜する人たちからみると、溜飲が下がる思いだろう。
しかし、こういうリベラル批判が効力を持つためには、前述したように、「リベラルとは何か」という概念定義がしっかり提示されていることが前提となる。
そこをあいまいにしながら議論を進めていくところに、私は多少の違和感を抱いた。
ただ、萱野氏の「リベラル派には最大の弱点がある」という指摘には耳を傾ける必要があると感じた。
その弱点とは何か?
「リベラル派の弱点は、“正義の実現” にはコストがかかる、ということを軽視しているところにある」
と、氏はいう。
具体的には、こういうことだ。
「リベラル派はしばしば、弱者のために(たとえば)生活保護をもっと拡充すべきだ、と主張する。生活保護だけでなくすべての社会保障をもっと拡充すべきだ、とも主張する。
しかし、『その予算を確保するために、私たちが負担する税金をもっと増やそう』とはなかなかいわない」
つまり、リベラル派は、口を開けば「人権の擁護」だとか「生活弱者の救済」などと主張するが、そのような “正義の実現” にはとてつもないコストがかかることを無視している、というわけだ。
そして、そういうリベラル派のコスト意識の欠如が、近年一般庶民から嫌われているという論法に、萱野氏はつなげていく。
氏がいうには、
「そのような “正義の実現” を可能にするのは、パイが拡大しているときだけである」
「パイ」とは、人々の間で分配しうる社会的資源のことだ。
すなわち、具体的には、税金を基本とする国の財源をいう。
パイの拡大期なら、リベラル派の主張は問題なく支持される。
日本でいえば、たとえば、1970年代半ば。
▼ 1960年代から始まった新幹線の整備は、70年代の日本の高度成長期を象徴する事業だった

萱野氏は書く。
「1973年、当時の田中角栄総理は医療や年金などの社会保障を大きく拡充した。なぜそうした政策が可能だったかといえば、高度経済成長によってパイそのものが拡大していたからである。
この時代は経済が大きく成長していただけでなく、生産年齢人口も増加し続けており、パイを拠出する国民一人ひとりの負担をほとんど増やすことなくパイの分配を手厚くすることができた」
が、「今は違う」と萱野氏。
「今の日本は少子高齢化が進み、70年代の高度成長期とはうってかわって、パイの縮小が大問題となっている」
つまり、リベラル派が主張するような、抽象的な「正義の実現」などが夢物語に思えるほど、財源がひっ迫している。
「リベラル派に対する風当たりが強くなってきたのは、理想論しか語らないリベラルな人々に対する庶民のリアリズムが反映されたものだ」
というのが、萱野氏が一貫して主張するテーマの骨子なのだ。
欧米においても、こういう “反リベラル” な運動が盛んになってきている、と氏は書く。
「ヨーロッパ諸国においても、極右政党が支持を伸ばしているのは、『財源が厳しくなり、われわれの福祉すらままならないのに、なぜさらに外国人を受け入れるのか?』という国民の反発があるからだ」
▼ 「ネオナチ」のような極右団体の登場も移民・難民増加への危機感が背景になっている

リベラル派は、こういう「反移民運動」を、しばしば「右傾化」、「全体主義化」としてとらえるが、そのような庶民の “右傾化” と思われるものこそ、実は、パイが縮小することへの庶民の危機意識から生じていると、萱野氏はいう。
確かに、この主張には一理ある。
欧米のことはいざ知らず、日本における「パイの縮小」は、まさに「少子高齢化」の進み具合が予想外に早くなってきたことに由来するからだ。
だが、そういうように、“鮮やかに” … つまり図式的に問題を整理されても、どこか腑に落ちないものが残る。
それは、けっきょく、「リベラルとは何なのか?」という根本問題が依然として残されているという不満に帰結していく。
私の思いを正直に書けば、社会風潮や国の政策に不満を表明した人に対し、「リベラルだ!」と “負のレッテル” を貼る発想には、やはり「全体主義的な匂い」を感じて、窮屈な気分になる。
テレビのある報道番組を見ていたら、アフリカや中東では食糧危機が生じ、餓死者も出ているというのに、世界の食糧供給量は十分に足りているはずだという。

では、なぜ食糧危機に見舞われる国や地域が出てしまうのか?
そこには、もちろん気候変動や内戦などの問題が絡んでいる。
しかし、いちばん大きな理由は、金融資本主義の発展により、食糧が投機の対象となったためだという。
けっきょくは、グローバル企業や富裕層のマネーゲームに「食糧」が使わているからだとか。
そういう話を聞いて、「そりゃおかしいだろ!」と声を出すことも、反リベラル勢力から見ると、“コスト意識の欠如” に映るのだろうか?
そう見られてもかまわないから、その代わりに、食糧問題とグローバル資本主義に対するしっかりした解説を受けたいと思う。
昔の萱野氏なら、そこまでキチッと説明してくれたはずなのに、この本では、そこをはしょってしまったという不満が残る。